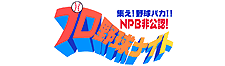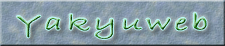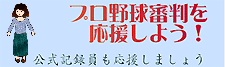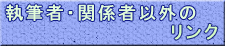NPBにおける受難の時代 by ICHILAU&MB Da Kidd
第1回 NPBにおける受難の時代 〜その1〜 ICHILAU
第2回 NPBにおける受難の時代 〜その2〜 ICHILAU
第3回 NPBにおける受難の時代 〜その3〜 MB Da Kidd
第4回 NPBにおける受難の時代 〜その4〜 MB Da Kidd
第5回 NPBにおける受難の時代 〜その5〜 MB Da Kidd
第1回 NPBにおける受難の時代 〜その1〜 ICHILAU
みなさまこんにちは。ICHILAUです。今回から2回にわたっては、2001年から2002年にかけての、『NPBにおける受難の時代』について考察してみたいと思います。
2001年から2002年にかけては、日本野球にとって厳しい時期が続いたといえるでしょう。
まずは、2000年のオフにポスティングシステムでMLBに移籍したイチロー選手が、2001年に大活躍し、ア・リーグMVPと首位打者、ならびに盗塁王に輝く一方、新庄選手がNPBに在籍していたときとはうって変わったように明るい表情でプレイし、日本の大勢の野球ファンの目を、MLBに向けさせました。
また、2001年11月には、IBAFワールドカップでNPB選手を大量に送り込んだ日本がメダルを逃すという失態を演じる傍ら、横浜の株式譲渡問題で、機構とオーナー会議が迷走し、大きく醜態をさらしてしまいました。
するとこの年のオフは、それを後目に、石井(ヤクルト・スワローズ)、田口(オリックス・ブルーウェーヴ)をはじめとする主力選手たちが、NPBで提示された好条件を蹴って、MLBへと旅立っていったのです。もともとNPBの人気低下は叫ばれていましたが、この2001年のイチロー・シンジョーショックは、その流れを決定づけたといっていいのではないでしょうか。
そして2002年には、FIFAワールドカップという名のサッカー台風が日本全国で猛威をふるい、野球が根づいていた日本の土壌に、文化的な損害のつめ跡を、大きく残していきました。野球ファンのみなさんの中でも、いまだにサッカーショックから抜けきれない方々はおられるでしょうし、またW杯以後、メディアにおけるサッカー露出が、いきなり増えた気がします。
では一方で、NPBはどうかというと、開幕から2ヶ月の間に星野新監督の下、快進撃を続けていた阪神タイガースの勢いが止まる傍ら、7月末日時点で2位に10ゲーム差をつけてペナントレースを独走している巨人は、ほぼ優勝を手中にしていて、8月上旬にもマジックナンバーが点灯しようとしています。したがって、このようにシラける内容のペナントレースを展開している結果、現状のNPBの人気低下傾向には、歯止めがかかるどころか、さらに拍車がかかったと言っても、私は大きく外れていないと思っています。
ですが現状は、これへの有効な対策が為される見込みはなく、「もはや、NPBは救いようが無い」との絶望的な意見も、最近はよく聞かれるようになりました。
しかし、今回のW杯について、先日のサッカー特集の出場国紹介をやらせていただいた際、私自身20カ国以上のサッカーリーグの現状についてさらに学ばせていただいた結果、自分のNPBに対する考え方は、すこし違ったものになってきました。
まず私が知ったのは、どの国のリーグも試合の観客動員やクラブの財政で苦しんでいることでした。
欧州で人気があると言えるリーグは、イングランド、イタリア、ドイツ、スペインの四大リーグに加え、トルコ、ギリシャ位なもので、後は欧州国際カップ戦で強豪クラブを迎えた場合か、少数の名門クラブの直接対決、いわゆる“クラシコ”でも無い限り、ガラガラと言うのがその実態です。
また、欧州に存在する殆どのサッカークラブは、入場料、放送権料、スポンサー料、会費、大会の賞金では財政を賄えず、選手をより裕福なクラブに移籍させた時に発生する移籍金無しでは、黒字はおろか、存続さえままならないという状態にあります。それに加えて、かなりのビッククラブでも、選手売却が最大の収入源になっているのが現状で、ACミランやレアル・マドリードなどのサッカー界の最高級に位置するクラブですら、実際には常に大きな赤字をだしており、それを親会社や行政に補填されながら、象徴としての地位を守っているのです。したがって、移籍金抜きに黒字をだせるサッカークラブは、皆無なのです。
そこで私は、
「選手の移籍金に頼ることなく黒字が出せるNPBは、かなり優良なリーグだ」
と考えるようになってきました。
さらにサッカーの世界では、“ボスマン採決”を筆頭に、移籍金制度に対して「人権を侵害している」との追及が相次いでいます。選手は、優柔不断なFIFAではなくEUに訴える事で権利を得ていますが、その過程で、移籍金制度自体が何時非合法化されてもおかしくないのが現状です。
ですが、この話はさらに長くなるので、次回に回したいと思います。
第2回 NPBにおける受難の時代 〜その2〜 ICHILAU
みなさまこんにちは。ICHILAUです。今回も前回に引き続き、『NPBにおける受難の時代』について考察してみたいと思います。
前回は、「移籍金なしに黒字の出せるクラブが皆無のサッカー界」と比較して、「選手の移籍金に頼ることなく黒字が出せるNPBは、かなり優良なリーグなのではないか」と考えるようになってきたところまでを書かせて頂きました。
そこで今回は、そのサッカー界の長年の問題である移籍金制度について、まず述べていきます。
サッカーの世界では、いわゆるMLBやNPBのドラフトであるような選手の契約金についての規定は、選手がプロに入る時点では、ありません。たとえば欧州のクラブユースで育成される選手にしても、クラブで認められ、プロ契約を結ぶ時点で決まっているのは選手の年俸だけで、クラブ側は契約金なしで、その選手の保有権を持ちます。また、ドラフト制度は、たとえば、2000シーズンまでのKリーグ(韓国)には存在していましたが、Kリーグのドラフトでは学校とクラブが”縁故関係”を結んで、クラブの親会社から学校側が金銭的支援を受ける、という形式を採っており、選手個人に契約金が支払われるわけでは、ありません。したがって2002年現在、殆どのサッカークラブに置ける最大の収入源が選手の移籍金であることは、前回お話したとおりです。なお、今日の欧州サッカー界では、ケーブルテレビの放送権料が高騰し、ビッククラブの場合は放送権料が収入の中で大きいシェアを占めているわけですが、それでも黒字となるクラブは例外なく、選手放出で得られる移籍金が、選手獲得で支払う移籍金を上回っています。
もちろん、中小クラブの場合、無尽蔵の赤字を物ともしないビッグクラブの金脈がこれらを支えるために、移籍金制度が無くてはならないものになっていることは前回も書かせて頂いた通りですが、近年は、この移籍金制度の前提となっている保有権が、選手の人権を侵害しているのではないか、という追及が相次ぐようになりました。
その嚆矢となったのが、以前の2002年W杯特集の際に説明させていただいた、ボスマン判決です。
ちなみにボスマン判決以前の保有権というのは、選手とクラブとの契約が切れても、まだクラブ側は選手の保有権を持っているので、選手が移籍したくても前所属クラブの許可無しには移籍できない、というものでした。すると当然ながら、契約終了後の選手が移籍しても、前所属クラブには移籍金が入るので、前述のとおり、クラブ側としては、プロ経験のない選手と1年契約をしただけで、好きなだけその選手を保有し、自分たちの事情で好きな時に移籍させることができるという、“とんでもないもの”でした。
したがって中小クラブとしては、なるべく高い金額でその選手を他クラブに売りつけることで収入を確保し、クラブとしての命脈を保ってきたわけです。
しかし、この“クラブ支配”の状況を一変させる事件が起きました。これがボスマンケースです。
1990年に所属クラブ、RCリエージュとの契約が切れたベルギーの無名選手、ボスマンは、新たなクラブへの移籍を希望しました。しかしその際、RCリエージュとボスマンとの関係はこじれ、RCリエージュはボスマンに法外な移籍金をかけ、彼を“飼い殺し”の状態にしてしまいました。
そこでこのような仕打ちを受けたボスマンが、ベルギーの裁判所へクラブの人権侵害を提訴すると同時に、この様な保有権制度を容認するベルギーサッカー協会、およびUEFA(ヨーロッパサッカー連盟)の移籍制度そのものの違法性を訴えると、この事態を重く見たベルギーの裁判所は、EU全体を管轄するヨーロッパ司法裁判所にこの判断を委ね、この件については、ヨーロッパ司法裁判所が判決を下すこととなったのです。そしてボスマン側が、保有権制度がEU法の定める「労働者の移動の自由を認め、労働条件における国籍による差別の禁止」に払拭すると主張する一方で、UEFAを筆頭とするクラブ側は、「移籍金が無くなると、クラブの財政に多大な負担がかかるので、クラブ間の競争力のバランスを乱し、サッカー界に危機が訪れる。また、サッカー選手はその労働の形態の特殊性から、一般労働者とは異なるので、特殊な立場にある芸術家として扱われるべきだ」と主張しました。
すると1995年には、クラブ側の頑強な抵抗にもかかわらず、ボスマンは圧倒的な勝利を勝ち取り、その結果、外国人枠と保有権が緩和されたことで、良いクラブに良い選手が集中し、クラブの試合が面白くなり、クラブサッカーへの関心が高まり、放送権料の高騰などを通して、サッカー界は潤ったのです。なお移籍金は、契約期間中に移籍する為に契約を破棄した際の「違約金」として生き残りましたが、華やかな国際カップ戦に縁のない中小クラブにとっては、自らの事情にしたがって選手を売却できなくなった分、リスクが増えただけでした。
それから、「労働者」としての地位を手にした選手達は、更に保有権に対する追及を強めました。
そして1997年には、EU圏外の国籍を持った選手についてもボスマンと同様の裁判が起き、EU以外でも「サッカーの制度が、労働法に触れる」との判断が出る見込みになったところで、重い腰をあげたFIFAはついにEU法などに触れない新制度の整備を始め、2001年に新たな規定を完成させました。
★ 国際移籍に関するFIFA規則
【前文】
契約が終了した全ての選手は、世界中で自由に移籍することができる。
ただし、育成補償金に関する下記の2の規定に従うものとする。
1 選手の育成に安定した環境を確保するために、18歳未満の選手の国際移籍または最初の登録は、一定の条件を満たした場合にのみ認められる。
2 選手の才能を増進し競争を促すためには、クラブが若い選手の育成に投資するための財政的および競技的な動機が必要である。原則として、23歳以下の選手の移籍には、クラブに対して育成補償金が支払われる。
3 契約期間は国内法に応じて最低1年から最高5年とする。クラブ、選手および一般大衆にとって、契約の安定は最も重要である。選手とクラブの契約関係は、サッカー特有の必要性に応じて、選手とクラブの利益の正しいバランスを計り、競技の秩序と適切な機能を 維持するような制度により統括されなければならない。
4 競技の秩序と機能を保護するために、1シーズンに2回の統一の移籍可能期間を設ける。移籍は1選手につき1シーズン1回を限度とする。
しかし、この制度でもまだ選手の自由は制限されており、選手自身や、選手と利害が一致する一部のビッグクラブの更なる追及によって、完全な自由が獲得される可能性もあります。そうなってしまえば、基盤を持たない中小クラブは多大な打撃を受けることでしょう。ハッキリ言って移籍金制度は時代遅れだと私は思いますが、中小クラブの移籍金に代わる収入源についての見通しは立っていないのが現状です。
そこで以上の事を考慮すると、私はむしろ、移籍金に依存しなければならないサッカーよりも「移籍金がなくても存続できるリーグ」=NPBの方が先を行っていると思います。
NPBは会社という強力な基盤に立脚し、親会社の営業目的と球団保有目的が一体化しているチームも複数存在するため、存続問題が起きることすら考えにくく、移籍金制度のような人権侵害と糾弾されている制度に頼らずともやっていけており、選手の権利と言う意味では、ドラフト制度導入前には10年選手制度も存在し、いまはFA制度もあるので、サッカーよりも人権が確保されているのではないかと考えるからです。それに前述したとおり、プロの世界に入る際には、特殊な場合を除き、契約金もちゃんともらえます。
もちろんNPBのあり方や将来について批判が聞かれるようになって久しいのは、皆さんもご承知のことですし、NPBにはNPBなりにプロアマ問題や、メディアとの癒着、チーム格差、閉鎖的すぎるシステムなどの、解決すべき問題を数多く抱えてはいますが、移籍金制度や保有権と言ったサッカー界の抱えている問題の方が遥かに深刻であり、競技自体を脅かしているのではないか、と私は考えているのです。
ただ、サッカー界の問題の方が深刻だからという理由で、NPBの問題が見過ごされていいわけでは決してありませんし、また、最近話題になっている、ビッグクラブのエゴの話や、メディア企業の破綻の話もあります。そこで次回以降はこれらの問題について、執筆者を編集長のMBさんに代わっていただき、サッカーや野球という枠を越え、スポーツビジネスのあり方の面そのものから論じていただくことにします。
【参考サイト・文献】
http://web.sfc.keio.ac.jp/~msh/sports-b/8th.htm
http://www.people.or.jp/~15oliseh/repo/repo1.htm
http://www.sportsnetwork.co.jp/jl/jl_advbn/vol35.html
http://www.sportsnetwork.co.jp/jl/jl_advbn/vol36.html
http://www.j-league.or.jp/nletter/66/02.html
2001年6月25日/日本経済新聞 朝刊23面より 『競争促すか(韓国Kリーグ)ドラフト撤廃』
南米蹴球紀行 ケイブンシャ
第3回 NPBにおける受難の時代 〜その3〜 MB Da Kidd
前回まではICHILAUさんにムリを言ってお願いして、サッカーの世界の話を元に、NPBというプロスポーツリーグがサッカーをよく知っている人間から見るとどのように捉えられるか、という話を2回に分けて、書いていただきました。そして、その具体的な結論は、これです。
”私はむしろ、移籍金に依存しなければならないサッカーよりも、「移籍金がなくても存続できるリーグ」=NPBの方が先を行っていると思います。
NPBは会社という強力な基盤に立脚し、親会社の営業目的と球団保有目的が一体化しているチームも複数存在するため、存続問題が起きることすら考えにくく、移籍金制度のような人権侵害と糾弾されている制度に頼らずともやっていけており、選手の権利と言う意味では、ドラフト制度導入前には10年選手制度も存在し、いまはFA制度もあるので、サッカーよりも人権が確保されているのではないかと考えるからです。それに前述したとおり、プロの世界に入る際には、特殊な場合を除き、契約金もちゃんともらえます。”
さて、この記述を読んで、あれ?と思われた方々もかなり多いでしょう。確かに、この記述に矛盾はありませんし、論理としては、完結しています。しかし、何かがおかしい。では、なぜ、野茂さんをはじめ、さまざまな選手はNPBを『捨てて』、アメリカに渡ったのでしょう?あるいは、なぜ『常識外れ』な手段を採ってまでNPBから選手を引き抜き、MLBへと移籍させた辣腕エージェント、ダン野村さんを英雄視する野球ファンが少なからずいるのでしょう?
もうひとつの発言を取り上げます。これは、東大出身のプロ野球選手として話題になった、元千葉ロッテマリーンズの小林至氏の著作、『プロ野球ビジネスのしくみ』(2002.7. 宝島社新書)の中、112ページから113ページにかけての記述です。
”プロ野球は、ソニーや、トヨタ、または朝日新聞と同じように企業です。その行動は、家電産業、自動車産業、メディア産業と同じように利益追求です。
ソニーがプレイステーションを生産し、朝日新聞が新聞を発行しているのと同じように、プロ野球は、スポーツイベント=試合を媒介として、利益を追求しているのです。
だから、いくら読売が経営的に安定しているからといって、そして地域性を取り入れることがモラル的に美しいからといって、それが読売の利益を損ねる行動であれば、ビジネスとしては失格です。それどころか、「株主の利益」が重視されるこの時代、株主への背信行為と取られかねないのです。
ICHILAUさんの出された結論は、論理としては完結していますが、この記述は商業本におけるプロの人間による記述であるにもかかわらず、そのレベルにすら至っておらず、大きな矛盾をいくつも抱えています。具体的にひとつずつ、挙げていきましょう。
第一に、企業が存在する一番大きな目的は、利益追求ではありません。したがって、その行動を利益追求のみに限定することは、社会に対する企業の役割を、きちんと考慮していないことになります。また、英語の会計学用語において、企業のことを何と呼ぶかというと、それは"Going Concern(ゴーイング・コンサーン、継続企業)"です。つまりぶっちゃけた話、企業の一番大切な目的は、大学で経営学や企業論を修めた方々の間では常識ですが、
『存続して、社会に対して責任を果たし、また社会に貢献し続けること』
なのです。その手段として利益追求を行う、これが企業です。利益追求を目的として、利益がある程度上がったら企業を解散する、という例外的なことをやったのは、有名どころでは、資本主義の黎明期におけるヨーロッパの大航海ベンチャー企業、あるいは近年のシリコンバレーにおける数々のインターネット企業、そして一部の投資ファンド企業ぐらいで、ほとんどの場合は、あくまで上記の目的ですし、また、長く伝統を創っていって人々に夢と希望を与え続ける、というスポーツ産業の特殊性を考えた場合、単なる利益追求というのはこれと大きく矛盾します。
第二に、『スポーツイベント=試合を媒介として利益を追求している』と述べておきながら、『いくら読売が経営的に安定しているからといって、そして地域性を取り入れることがモラル的に美しいからといって、それが読売の利益を損ねる行動であれば、ビジネスとしては失格です。』と述べているのは、論理として最初から壊れています。
まずここには、広告・宣伝手段として、あるいは、営業の手段として、親会社がプロ野球の球団を利用している、ということが明記されていないどころか、スポーツイベント=試合を媒介として利益を追求している、と限定して述べられています。したがって、親会社が出資して、スポーツイベント=試合を行っている、自立した球団が前提で話が進められているというわけです。つまり、こういう書き方をするということは、日本独特の、プロ野球の球団を宣伝・広告手段として、あるいは、営業の手段として保有するという、親会社フランチャイズ方式を否定するということになっているので、それが読売の利益を損ねるケースもありえます。
なぜなら、読売の利益ということに絞って考えると、費用対効果ということを考えた場合、自立した球団に出資をするだけということが必ずしも利益追求にはならないし、また、利益を喰いつぶすブラックボックスにもなりかねないからです。それとこれは、広島カープや横浜ベイスターズ以外の10球団のあり方とはちょっと異なり、実態から大きくかけ離れていることにも、なっているのです。
第三に、『地域性を取り入れることがモラル的に美しいからといって、それが読売の利益を損ねる行動であれば、ビジネスとしては失格です。』というのは、『スポーツイベント=試合を媒介として利益を追求している』ことと、マーケティングの面から矛盾しています。
地域性を球団の名前に取り入れるのは、モラルではなく、あくまでマーケティング上の戦略です。地域の名前にした方が親しみやすいというのは、その球団がある地域住民の皆さんにとっては当然のことで、会社の名前に愛着を持つのは、ほとんどの場合、その会社に勤めている方々や、あるいはその会社と直接的・間接的にいい関係を持っていて、その会社に対していい印象を持っている方々ぐらいで、他の方々にはまったく関係がありません。したがってこれは、立派に営業戦略として成り立つわけで、逆に、地域性を球団の名前に取り入れず、代わりに企業の名前を入れるということは、その企業が国の誇りや地域の誇りとして認知されている特殊なケースを除き、反感を持たれて終わるのが、せいぜいです。つまり、球団の名前に企業名を取り入れるというのは、ほとんどの場合、『スポーツイベント=試合を媒介として利益を追求している』という利益追求目的に反することになりますし、こういう行動こそ、『ビジネスとしては失格』なのです。また、これによって営業成績が大きく落ち込み、利益を損ねた場合には、当然、株主への背信行為となります。
では、今回は次回へのイントロダクションとして、ここまでにしておきます。次回はいよいよ、この『NPBにおける受難の時代』というテーマの核心である、日本独特の、広告・宣伝手段として、あるいは、営業の手段として、親会社がプロ野球の球団を利用するという、私が命名したところの『カイシャフランチャイズ』、つまり親会社フランチャイズ方式の是非について、述べていきます。
第4回 NPBにおける受難の時代 〜その4〜 MB Da Kidd
さて、今年の日本シリーズ選手権のあまりものライオンズのふがいなさに怒り心頭だったかもしれない方々は多かれ少なかれこのメールマガジンの読者のみなさんの中にもいらしたかと思いますが、そういった、何か煮え切らずに悶々としていた方々に、その終了後、早速爽やかな朗報が届きましたね。もちろん、巨人の松井秀喜選手のFA宣言、そして、MLB挑戦です。私は、彼がどれだけやれるかは、彼が日本で培ってきたものをどれだけいい意味で捨てられるかが大きな鍵を握っていると思いますが、彼にその覚悟があるのなら、彼は間違いなく成功すると思います。ただし、MLBでは、1年目に結果を出すことよりも、長くスターとして君臨することの方が想像を絶するほど大変で、だからこそMLBは、世界最高の野球リーグであるわけです。そして私としては、松井選手にはなるべく長く、その厳しい世界でのスターであり続けてほしいと願っていることも、つけ加えておきたいと思います。
では、前置きはこれぐらいにして、今回からの本題、日本独特の、広告・宣伝手段として、あるいは、営業の手段として、親会社がプロ野球の球団を利用するという、私が命名したところの『カイシャフランチャイズ』、つまり親会社フランチャイズ方式の是非について、述べていきたいと思います。
前回において、企業の大きな目的が、利益追求という手段を通じて、
『存続して、社会に対して責任を果たし、また社会に貢献し続けること』
であることはすでに指摘しました。ですが、私は決して、企業は社会の市民であって、よき一市民として個人と同様にボランティア活動をやるべきだ、とか、利益を度外視して社会に貢献せよ、と言いたいのではありませんし、そういうところから話をしたいのでもありません。利益追求は企業の目的ではないにせよ、存在意義であり、そこが、企業と他の*法人とのまったく異なるところで、しかもこれは法律で規定されていることですから、それを否定することは、具体的なケース説明と条文は省きますが、法律違反ということになります。
企業は、倫理といった曖昧なものに基づいて動くのではなく、法律上の権利・義務関係に基づいて動くのが当然である、というのが私の意見です。したがって、もしも利益追求という目的以外の行動に企業を動かすのなら、企業に対して意見するのではなく、政治家に意見して、企業行動を法律によって規定するのが、その適切なあり方だと私は考えています。
* 法人 法律上で、権利・義務関係を整理するために、組織に対して、仮に与えた人格のこと。
ところが、日本の1990年代初頭のバブル期にはやった言葉に、メセナ活動というものがあります。これは、私自身が定義しますと、
『芸術文化擁護・支援活動を意味するフランス語で、古代ローマ皇帝、アウグストゥスに仕えたマエケナス(Maecenas)が詩人や芸術家を手あつく擁護・支援したことをその語源とし、大きな財力を持つ者が、文化を育て、発展させるために、自らの利益追求の有無に関係なく、私財を投じること』
であり、どれだけお金をつぎこんだらどれだけ儲かるか、ということを大前提として行動する企業活動とは、まったく異なるものです。ちなみに企業メセナ活動協議会(http://www.mecenat.or.jp/)によれば、
『ただし、現代の企業メセナにおいては、企業のイメージアップ・企業文化の改善・社内での連帯感・顧客との新たなコミュニケーションなど、長期的かつ間接的なメリットを求めることが企業メセナの当然の方向性である。
日本では1990年の企業メセナ協議会の設立に際し、テレビ番組の協賛の意で使用されてきた“スポンサー”という英語ではなく、フランス語のメセナを採用したことから、メセナは、企業がパートナーシップの精神にもとづいて行う芸術文化支援をさす言葉として知られるようになった。』
ということのようですが、これは純粋なメセナとは違うもので、明らかに広告・宣伝活動ですから、効果がどれだけあるかは別として、当然、利益追求のひとつの方法、ということになります。
そこで、話を企業スポーツやカイシャフランチャイズに戻すと、企業がスポーツ活動を支援する、あるいは、プロスポーツチームを持つ、ということは、決して、上記の私自身が定義した、メセナ的な考えに基づくものではありません。無論、利益追求のため、広告・宣伝活動の一貫としてやっているのです。
しかしそのことを論じる前に、企業の利益追求活動とは一体何なのか、そして利益追求のあり方とは一体どういうものなのか、ということについて言及しておく必要が、あります。また、これの違いによって、企業のあり方というものが、最初のプロ野球団が創設された大正時代と戦後とで異なっているということ、ならびに、戦後の日本の企業のあり方が、他の資本主義国における企業のあり方とぜんぜん異なることについても、言及しなければなりません。したがって次回は、そのことについて説明し、そのことが日本の企業スポーツのあり方にどう影響しているのかについて説明する際の、土台を述べていきたいと思います。
第5回 NPBにおける受難の時代 〜その5〜 MB Da Kidd
前回は、メセナの定義について言及し、現代の企業スポーツが、メセナ活動のコンセプトとは異なることについて述べました。そして今回は、企業の利益追求活動の違いによって、戦後日本における企業のあり方というものが、利益追求活動の面から、戦前の日本企業のあり方、ならびに、他の資本主義国の企業の企業のあり方とどう異なるのかについて言及し、さらにこれが、日本の企業スポーツにどういう影響を与えてきたのか、ということを説明する際の土台を述べていきます。
企業というものは、お金をたくさん持っている資本家という人たちが、それぞれのお金を寄せ集め、これらを元手にして創った、利益を追求するための組織です。そして資本家たちが目指しているのは、元手となったお金が、さらに増えて、戻ってくることです。したがって、最初の株式会社が1602年にオランダで設立された、大航海時代(17世紀)のヨーロッパにおける初期資本主義社会では、企業というものが設立されたのは純粋に利益追求のためで、大航海事業を行って、世界各地で貿易を行い、その結果獲得した産物を売り払って、さらに儲けるということを目指したものでした。ただし、このような大事業のスポンサーになることが、一人の大資本家だけでは難しいために、大資本家たちがお金を持ち寄って、組織を創り、これらが前回用語説明でも触れさせていただいた、『法人格』を持った。これが企業のはじまりです。
ところが、時代が過ぎていくにしたがって、このアイデアを応用して、さらに小さなお金を集め、大きな事業を起こそう、という動きが出てきます。そして、上記の大航海時代の事業に参加できたのが大資本家の連中のみであったのとは異なり、中小の資本家たちが多数参画して、お金を広く集め、事業を行うことが主流となっていきます。これが、18世紀から19世紀中ごろにかけて起こり、イギリスを中心とするヨーロッパの国々における産業革命を支えた、お金の面での動きです。しかし、これらは大きなお金を必要としながら、事業として活動する際、法人格を認められていませんでした。法人格を認められるには、各国議会での承認を必要としたのです。したがって、こういった事業は社会的な存在として認知されていなかったがために、法制度の枠の外に置かれてしまったので、社会不安や不正行為の温床となってしまいました。そこでイギリスでは1844年、株式会社法を制定して、*登記行為だけで法人設立を認めることにしました。これが、企業が社会的な存在として認知されたことのはじまりです。
*登記行為 役所に届け、届けた事柄を登記簿というものに載せてもらうことによって、法的な事柄として認めてもらい、法的・制度的な保護を受けられるようになること。
したがって、このシリーズの第3回でも述べたとおり、この株式会社法が制定された時点で、企業の目的は、利益追求を手段としながら、
『存続して、社会に対して責任を果たし、また社会に貢献し続けること』
となったのです。
しかし、企業はその歴史的な成り立ち上、利益追求はあくまで手段でありながら、その存在意義でもあるので、これを無視した活動はできません。したがって、企業活動で大きく儲けた人たちが、その儲けの一部を社会に還元する、といった、フランス語でいうノーブレス・オブリージュや仏教でいう喜捨などのコンセプトに基づき、第4回で私が定義したメセナ的な行為を行うのは、企業人としての面をあまり出さず、一個人として、企業活動とは離れたところで行うのが、一般的なあり方になるわけです。
ところが、戦後の日本では、上記のような利益追求というコンセプトとはまったく異なる企業群が誕生します。それが、官庁による手厚い保護とそのコントロールを受けた護送船団銀行連を基本とした、『日本株式会社』に属する企業群です。そこで次回は、企業スポーツとカイシャフランチャイズの基本となった、この『日本株式会社』に属する企業群について述べていきます。
【参考文献】
友岡賛(ともおかすすむ)著 近代会計制度の成立 有斐閣 1995年