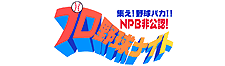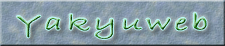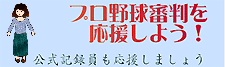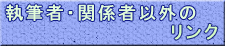Team Chronicles 〜日本のプロ野球チームの歴史〜 北海道日本ハムファイターズ編 by アトムフライヤー
第1回 その1:セネタース〜フライヤーズ編(1945-1960)
第2回 その2:フライヤーズ全盛期から凋落まで(1961-1971、大川博オーナー死去まで)
第3回 その3:日拓ホーム→日本ハムへのオーナー企業の交代、そして張本放出まで(1973-1975)
第4回 その4:新生ファイターズによる再出発、初の後楽園日本シリーズ、そして現在に至るまで(1975-2006)
第1回 その1:セネタース〜フライヤーズ編(1945-1960)
さて、いまは日本シリーズたけなわですが、読者のみなさまは、2006シーズンにおけるパ・リーグの覇者、北海道日本ハムファイターズの歴史についてどれだけご存知でしょうか?私は、近年は次第に知名度が上がってきていることからチームのフランチャイズ地域に根付きつつあるパ・リーグの各チームも、チームを所有する会社の変遷に伴い、過去の歴史が抹殺されてしまってきていることもあって、その歴史についてご存知ない方も多くおられるのではないかと思いました。
そこで私は、編集長のMBさんと数回にわたって打ち合わせを行い、チームの歴史シリーズを特別編としてぼーる通信にて配信することにいたしました。まずは、日本のプロ野球では比較的知名度が低い球団を中心に取り上げていこうと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
ファイターズのルーツは、戦後の混乱期の1945年11月にまで遡ります。この時期、戦前に解散した東京セネタースの監督を務めた横沢三郎を中心に、セネタースとして戦後再開したプロ野球にいち早く加わりました。当時の日本プロ野球連盟に加わっていたチームは、*1東京巨人軍、阪神、阪急、近畿グレートリンク、中部日本、ゴールドスター、太平パシフィックでしたが、セネタースはその一員となったのです。
ちなみにこの第2次セネタースは、戦前のセネタースを共同で所有していた貴族院議員の有馬頼寧やその弟の安藤信昭、ならびに西日本鉄道との資本関係はなく、会長には貴族院議員の西園寺公一が就任していたのですが、第2次セネタース設立の中心となっていた横沢三郎が東京セネタースの監督を勤めていたことから、セネタースの名前を引き継ぐような格好となったのです。
また、戦前のセネタースと同様、監督には球団の代表でもあった横沢三郎が就任しましたが、選手には、その弟で内野手の七郎をはじめ、社会人野球からは日立航空の飯島滋弥、東京六大学の慶應義塾大学からは白木義一郎、そして、戦争のため、試合に出場しないまま明治大学を中退した大下弘等を迎えて、チームはスタートしています。
*1 東京巨人軍、阪神、阪急、近畿グレートリング、中部日本、ゴールドスター、太平パシフィック
1946年当時のセネタース以外の各チームの呼び名はこうであった。ちなみに翌年から、阪神は大阪タイガースに戻り(1939年までは大阪タイガースと名乗っていた。大和球士氏の“野球五十年[時事通信社、1960]”によれば、もともと阪神電鉄が巨人の前身である大日本東京倶楽部の”東京“に対抗する意味で、大阪タイガースとチーム名を名づけている。阪神タイガースになったのは1961年から)、阪急は球団名を公募して、ブレーブスと名乗っている。中部日本も中部日本ドラゴンズ、近畿グレートリングも南海ホークスと、戦後プロ野球ファンのみなさんにもお馴染みの名前が登場する。
翌年、プロ野球が復活して最初のシーズンである1946シーズンには、エース白木、飯島、大下等が活躍しましたが、読売巨人軍や阪神のようにプロ野球経験者がかなりの数加わっていたわけではなかったセネタースは、8チーム中5位に終わります。また、チームが低迷した原因は、経験不足ということに加えて、シーズン中から身売りの話がささやかれたために、選手が動揺していたということもありました。そしてシーズン終了後、球団は、経営不振から東京急行電鉄に身売りし、代表だった横沢監督と横沢七郎は去っていったのです。チームのオーナーには大川博が就任し、チーム名をフライヤーズと変えました。
続く1947シーズンは、戦前のスター選手だった苅田久徳がプレイングマネジャーとしてチームを率いますが、選手層の薄さから6位に終わっています。
ところが1948シーズンは、様相が一変します。中日から小鶴誠、金山次郎、野口正明等が移籍で加わったのです。これは、いずれどこかでお話しすることもあろうかと思いますが、いわゆる中日のお家騒動の末に小鶴等8人が新球団大映スターズに移籍を試み、新球団の主力として再出発しようとしたところ、連盟が大映の参加を認めなかったために、東急に選手を貸し出す形で移籍してきたのでした。球団名も急映フライヤーズとなり、戦力的には優勝を充分狙える陣容が整いました。
しかし、実力で勝る中日からの移籍組がレギュラーの大半を占めたため、世間からは「中映ドライヤーズ」と呼ばれ、そのこともあってか、東急の生え抜き組と移籍組の折り合いが悪く、チームはバラバラになってしまい、結局5位に終わります。
1949シーズンは、大映が経営危機の金星球団を買収し、経営から離れたため、再び球団名は東急に戻りましたが、中日からの移籍組とともに看板のひとりだった飯島をいっしょに引き抜かれて、戦力、人気は低下します。監督は、前年まで阪急の助監督兼選手で活躍した井野川利春がプレイングマネジャーとして率いますが、主砲大下の前半の不調が響いて、8チーム中7位で終わりました。
そして、1949年のシーズンオフ。新球団毎日オリオンズ、近鉄パールスの加盟を巡って既存8球団が賛成・反対に分かれて対立すると、新球団の加盟に反対した巨人を中心とした球団がセ・リーグに集まり、賛成した南海、阪急、毎日を中心にした球団がパ・リーグに集まって、既存の1リーグが2リーグに分裂しました。この結果東急は、阪急、南海を中心とした電鉄リーグの誘いからパ・リーグに参加することとなります。
またこのシーズンオフは、球団の数が倍近く増えたために既存球団からの引き抜きが激しくなり、阪急ブレーブスとともに引き抜きの標的にされた東急フライヤーズは、大下、白木、皆川定之、常見昇、浜田義雄は残ったものの、黒尾重明、森弘太郎、片山博、長持栄吉、大沢清、清原初男、塚本博睦等の主力選手を失ったため、大幅な戦力低下となってしまいました。
すると翌1950シーズンは、監督には戦前社会人野球で活躍した安藤忍を迎えますが、戦力の低下から6位(7球団中)に終わりました。2リーグ分裂後のこの順位なのですから、1リーグ時代、8チームの6位とは事情が異なります。のちにパ・リーグが6球団となっていることを考えると、戦力が整わない新球団である近鉄パールスのおかげで最下位を免れているだけですから、実質的には最下位も同じでした。ちなみに活躍したのは、首位打者とベストナインに選ばれた大下と常見、浜田くらいではあったのですが、新鋭の米川泰夫が台頭し、23勝をあげて気を吐きました。
1951シーズンは安藤が総監督になり、再び監督は井野川に戻りましたが、新戦力の補強がほとんどなく、相変わらず戦力の整わない近鉄パールスの不振がひどいので最下位こそ免れているものの、弱小球団であることには変わりありませんでした。以後、豪放磊落男として知られ、南海軍の創設に関わった岩本義行が監督に就任した1956年までは、最下位から2番目が定位置になり、東京を本拠地としながら人気の巨人に比べると存在感のない、不人気球団のひとつとなってしまったのです。
またこのシーズン、低迷する球団の人気を支えたのは主砲大下でしたが、シーズンオフに借金の問題による感情的な行き違いで球団と対立し、大騒動になります。すると大下の移籍を巡って、西鉄ライオンズ、近鉄パールスが争奪戦に参加。裏金が飛び交い、あまりのひどさに一時は大下の任意引退もやむなし、としというところまできますが、大物政治家の介入で、球団による譲渡の契約のあるライオンズへ、緒方俊明ならびに深見安博との交換移籍が決まり、1952年のシーズン中に大下はチームを去っていきます。大下との交換で移籍してきた緒方と深見はともによく働き、特に深見はこの年に最多本塁打のタイトルを獲得したのですが、いくら成績を挙げたところで人気は大下に遠く及ばず、ますます地味なチームになってしまいました。
1954年からは東急電鉄が経営から手を退き、同じ東急グループにあった映画会社の東京映画配給(東映)が、経営に乗り出します。ただしこの際、オーナーは代わっていません。大川博オーナーはすでに1951年から東映の社長に就任していたからです。
ちなみにこのシーズンからは、当時巨人・国鉄スワローズ・毎日オリオンズの3チームもホームにしていたため、観客動員力がなかったことを理由に後楽園球場の使用ができなくなってしまったことから、東映は独自で駒沢球場を建設し、チーム強化のため、積極的に新人選手の補強を行いました。1954年から1959年にかけて、毒島章一、安藤順三、土橋正幸、久保田治、山本八郎、石原照夫、西園寺昭夫、吉田勝豊、張本勲といった後の主力選手を入団させ、助っ人外国人選手として、ジャック・ラドラも獲得しています。
1957シーズンと1958シーズンは連続して5位でしたが、1956年のシーズンオフに東急時代から中心だった米川、浜田がチームを去ると、主力が、東映が補強した選手になりました。特に1958シーズンは、毒島、ラドラ、スタンレー橋本、土橋等がオールスターに選ばれ、毒島と橋本がベストナインになり、土橋が21勝をあげるなど、個人の成績が上がってきたのです。戦力的には次第に整いつつありました。「駒沢の暴れん坊」の呼び名が定着しだしたのもこのころです。
1959シーズンは、新人張本の活躍がチームを活性化させます。張本は、野球部の暴力事件に巻き込まれ、野球部を途中で退部したため、中央でこそ無名でしたが、巨人の水原監督がその打撃能力を買っており、事件がなければ巨人に入り、開幕から一軍を約束されていたと言われるくらいの実力者だったので、19歳ながら6月には四番に座り、活躍しました。また西園寺、橋本、吉田、土橋等も成績を伸ばしたので、チームとしても球団創設以来、初めてAクラス(3位)に入ったのです。ちなみにこの年、張本が球団初の最優秀新人選手に選ばれています。もはや誰もフライヤーズを弱小球団とは呼ばなくなっていました。
しかし期待された1960シーズンは個人プレーが目立ち、チームとしてまとまりがなかったので、結果的には5位に終わっています。
次回はフライヤーズの全盛期、そして、その影の立役者としてフライヤーズを支えてきた大川博オーナーが逝去されるまでの話です。
第2回 その2:フライヤーズ全盛期から凋落まで(1961-1971、大川博オーナー死去まで)
さて、前回はチームの創設から次第に強くなって行き、現在もブラウン管にたびたび登場する張本勲氏や土橋正幸氏らが登場するところまでの話をさせていただきましたが、今回はそこからフライヤーズ初優勝、そして凋落〜身売りに至るまでの軌跡を追っていきます。
1960シーズンのオフに球団は、岩本義行に代わり、前巨人監督だった水原茂を監督に就任させました。すると水原は、チームプレーを徹底させ、1961年のシーズンに臨みます。
そして翌1961シーズン。フライヤーズは南海ホークスと首位争いをするなど大きく躍進したため、優勝の呼び声もかかるようになり、同時期にセ・リーグで優勝争いをしていた巨人との、史上初となる東京での日本一決定戦も期待されるようになります。これに伴い、弱小の東急時代を知るファンからは、「銀座シリーズ開催」との歓声があがってきましたが、この年は結局南海ホークスの底力に屈し、2位に終わったのでした。ただ一方で選手たち自身は、やればできるという自信がつき、翌1962シーズンに期待がかかりました。
そこでフロントは、シーズンオフに安藤元博、青野修三、岩下光一、種茂雅之、尾崎行雄と大がかりな補強を行います。なかでも、甲子園の優勝投手で、高校を中退させてまで獲得した尾崎は、のちの大活躍を考えると、フロントの大きな得点といっても差し支えないでしょう。おりしも、東京オリンピックの競技場建設のために本拠地である駒沢球場を取り壊されてしまった「駒沢の暴れん坊」たちは、新たな本拠地である神宮球場をはじめ、各球場でその力を発揮することになったのでした。
1962年のシーズン、フライヤーズは開幕から六連勝と波に乗ります。青野、岩下、種茂等の新人の活躍に刺激され、毒島、張本、吉田、西園寺等も力を発揮し、相手球団の投手を打ち込みました。投手は、土橋、久保田等もがんばりましたが、なんといっても新人尾崎の快投が目立ちました。当時パ・リーグを震え上がらせていた*2大毎オリオンズのミサイル打線、榎本、山内、葛城と続く3、4、5番相手に、直球だけで三者凡退に押さえるという派手なデビューをし、途中では指のマメに苦しんだものの、最終的に20勝をあげています。そして南海ホークスと西鉄ライオンズという常勝チームを振り切り、念願の初優勝を果たしました。
この快挙に、古くからのファンは大喜びしました。ただ、日本シリーズの相手は、24年ぶりの優勝という阪神タイガースとなり、巨人は四位に沈んでしまったため、史上初の東京シリーズはお預けになったのです。
*2 大毎ミサイル打線
2番・田宮謙次郎、3番・榎本喜八、4番・山内和弘(現在は一弘)、5番・葛城隆雄と続く、切れ目のない打線のこと。特に4番の山内(打者として初の名球会会員)、3番の榎本が2,000本安打を放ち、葛城も1,745安打を放っていることを考えると、確実性のある打撃をしていたのではないかと思われる。ただし、決して単打ばかりのピストル打線ではなく、山内が1960シーズンには32本塁打を放つなど、いざとなれば一発が出る、コワい打線でもあった。
日本シリーズは甲子園での1、2戦こそ落としましたが、神宮での第3戦にて引き分けると、第4戦は新人安藤の力投で初勝利を得、第5戦は延長戦の末、岩下のサヨナラ本塁打で対戦成績をタイに持ち込んで、波に乗りました。そして第6戦もこのまま勝つと、第7戦は延長戦の末、西園寺が決勝本塁打をはなち、ついに東映は日本一になったのです。チーム創設以来、苦節16年ではじめて勝ち取った栄光でした。
このとき、これを受けて大喜びした大川博オーナーが背番号100のユニフォームを着て優勝パレードにのぞむと、大きな話題になりました。人前で目立つことが好きではなかったという話もある大川オーナーではありましたが、自らが苦労し、いろいろと模索しながら東急グループを五島慶太総裁に代わって支えていた時代、創設1年目のチームのオーナーに就任してから15年、永年手塩にかけてきたフライヤーズの優勝には、感激もひとしおだったのでしょう。日本シリーズの最優秀選手は土橋正幸と種茂雅之が史上初の2人受賞となり、また、リーグ最優秀選手には張本勲が選ばれました。ベストナインには張本と吉田勝豊が選ばれています。暴れん坊軍団の絶頂期でした。
しかし、以後1963シーズンから1967シーズンまでは、Aクラスこそ確保するものの、優勝には至りませんでした。その最大の理由は、優勝したことによる選手の年俸高騰に球団が補強費を惜しむようになったためです。
優勝すれば人件費がふくらみ、球団経営が苦しくなる。逆に人件費を削れば球団の力は落ち、収益が減って、やはり経営が苦しくなる。これは、新たな球団の収益源になりつつあったテレビの放映権料による安定した収入を得られなくなってきた、すべてのパ・リーグ球団が抱えていた悩みでした。これにより、毎日オリオンズ、南海ホークス、西鉄ライオンズと一時は絶頂を極めた球団の数々は次第に凋落していき、東映フライヤーズもその例外ではなかったのです。
この5年間で、吉田勝豊、山本八郎、西園寺昭夫、久保田治等は放出され、土橋正幸は引退しました。駒沢の暴れん坊たちは一人抜け、二人抜けして、次第にグラウンドから姿を消していったのです。大杉勝男、白仁天、大下剛史、森安敏明、高橋善正といった新戦力が入団し、徐々に世代交代は進んでいきましたが、巻き返してきた南海ホークスや、次第に力をつけてきた阪急ブレーブスの前には力不足でした。
そんな中、1967年末に水原監督が辞任します。補強費をめぐり、節約をとなえる球団側との対立が主な原因でした。後任として監督に就任したのは、西鉄三連覇の中心打者で、OBの大下弘。大川オーナーは、当時全国ネットでのテレビ中継との連動効果で急激に人気が高まりつつあった巨人に対抗するため、人気のあった大下を監督に据えたのです。何とか球場に観客を呼び戻そうという作戦でした。そして大下は大川オーナーの命を受け、かつての西鉄ライオンズの流れを組む、「三無主義(門限無し、罰金無し、サイン無し)を打ち出し、人気回復を図ります。豪放磊落さでもって球団を活性化させよう、暴れん坊といわれた元気を復活させよう、それが大川オーナーの狙いでした。当時、ドジャースの戦法をベースにした管理野球で時代を席巻しつつあった川上巨人に対するライバル宣言でもあり、その具体的なやり方として反管理野球、反スモールベースボールをスローガンとして打ち出し、全盛期のチームのイメージを踏襲しようとしたわけです。
しかし、待遇の悪さ、人気のなさに嫌気がさしていた選手たちにはむしろ逆効果で、1968シーズンはダントツの最下位、加えて、チームの主力選手の中に八百長の疑いが濃厚な者も出現し、チームはバラバラになってしまいます。いまでこそ黒い霧事件の影響から八百長と言えば西鉄ライオンズが有名ですが、以前から東映にもその疑いありとのうわさが絶えず、昭和三十年代には疑いのある選手が放出されたり、解雇されたりしています。
そこで大川オーナーは当時、特にうわさのあった主力選手2人と直接話をして真意を問い質すほどでした。大川オーナーとしては、永年愛着のあるチーム。気になって仕方がなかったのでしょう。
また大下監督は、代打を出すときに選手にジャンケンで決めさせるなど采配にも迷いが目立ち、ポケットマネーで選手に飲み食いさせてチームを掌握しようとしましたが、これは逆効果でした。監督と選手との間に上下のけじめがつかなくなり、選手は監督を侮るようになって、どんどん心が離れていったのです。そのうち選手間では、「監督がオーナーに、悪いのは選手だ、と泣きついている」という噂さえたつようになります。そこで大下監督はこの状況を何とか改善すべく遠征時に主力選手たちを呼ぶと、「チームの不振を君たちになすりつけるつもりはない。これからもがんばってくれ。これが、私が君らを裏切らない証拠だ」と言って右腕に短刀をつき刺して見せたりしたのですが、いくらこんな任侠映画まがいのことをしても、グラウンドで迷いなくきちんと仕事ができない人間に選手たちの心をつなぎとめられるはずはなく、チームの建て直しに失敗し、シーズン途中、志半ばにしてチームを去っていきます。
1969シーズンは、元阪神タイガースの闘将・松木謙治郎を監督に迎えますが、チーム状態は相変わらずで、新人金田留広の活躍こそあったものの投手陣がくずれてしまい、西鉄ライオンズと南海ホークスの不振がひどかったために目立ちませんでしたが、4位になるのが精一杯で、明るい話題といえば、新人でオールスターに出場した金田が実兄である巨人の金田正一と史上初の兄弟対決を行ったことくらいでした。ちなみにこの年のパ・リーグは、かつてBクラスの常連だった阪急ブレーブスと近鉄バファローズが優勝を争い、何度も優勝を争った南海ホークスと西鉄ライオンズが最下位を争うという逆転現象が起きて、ファンも時代の変化を感じていたのです。
そして、シーズン後半で西鉄ライオンズの選手たちによる八百長事件が明るみに出ると、翌年には東映フライヤーズもこの黒い霧事件に巻き込まれていきます。マスコミにもオーナーにも「八百長は絶対にしていない。」と宣言した二選手に、野球賭博の胴元の使者からの金銭の受け渡しがあったことが警察の調査で判明したため、コミッショナー裁定によって一人が球界から永久追放になります。また、もう一人も追放は免れたものの、首脳陣からは信頼を失い、やがて追放に近い形で他球団に放出され、プロ野球の世界を去っていったのでした。
結局処分されたのはひとりでしたが、信頼していた選手に裏切られた大川オーナーの嘆きは大きく、この事件発覚以後、球団経営に情熱を失っていきます。西鉄ライオンズに比べて処分者が少なかったことからあまりこのことはマスコミでは大きく取り上げられていませんでしたが、黒い霧事件は、東映フライヤーズをも崩壊させていったのです。
その結果、1970シーズンはスタート時こそ好調でしたが、黒い霧事件の影響があったことから、前半の半ばで失速してしまいます。打撃陣は好調で、中でも張本・大杉は巨人のON砲の69本塁打198打点を上回る78本塁打229打点を挙げており、他にも白が18本塁打64打点、大下剛史が3割をマークしましたが、投手は金田以外壊滅状態で、守備と走塁はまるでダメ。いわゆる大勝・競り負けをする下位チームの典型例で、勝負が見えると個人プレーに走るため、数字はすごくてもチーム力は脆弱で粘りがなく、この点で優勝したロッテオリオンズに大きく及ばなかったため、5位に終わったのでした。
1971シーズンは、大阪タイガース・大毎オリオンズ時代に巧打者として鳴らした田宮謙次郎を監督に迎えます。打線は去年に引き続いて調子よく、日本新記録の5打者連続本塁打を5月に記録するなど相変わらずの状態のよさでしたが、投手陣がダメなことにも変わりはなかったので、金田の他には新人の皆川康夫ががんばったものの、他の投手は不調で5位に終わりました。7月には2軍選手が集団で門限破りを行い、大量に処分される事件が発生。前年には白が判定を巡って審判を投げ飛ばして出場停止になるなどのことを考え合わせると、かつての「暴れん坊軍団」は、グラウンドを所狭しと暴れまわる小気味いい豪放磊落さを持つチームではなく、Bクラス常連の乱暴なだけのチームに変わってしまっていたのです。この結果、同じ後楽園を本拠地としながら“球界の紳士たれ”を徹底し、川上監督の下で9連覇を驀進していた巨人との人気の差は開くばかり。選手も個人の成績優先で、下位低迷も当然でした。
1972シーズンは、張本、大杉、白のクリーンアップが3人で90本塁打270打点を稼ぎ、移籍の坂本敏三、加藤俊夫も活躍しましたが、投手が金田と森中通広以外ダメで、4位。一方でシーズン前に放出した大橋譲が阪急ブレーブスの優勝に大きく貢献、南海ホークスに放出した江本孟紀が16勝をあげるなど、ファンからは「選手の使い方もわからないのか」と非難を浴びます。
この1968〜1972シーズンという低迷期の間のハイライトは、1971年に皆川康夫が新人王に選ばれ、大杉が1969−1970年に本塁打王、打点王を獲得、張本が1967年〜70年まで首位打者を獲得し、1970年にシーズン最高打率を更新したことです。また1971年には、1967シーズンの新人王、高橋善正が完全試合を達成しています。
しかしながらこの時期は、確かに個人成績は派手なのですが、チーム力に粘りがなかったため、優勝どころかAクラスさえもほど遠い状態でした。
そんな状況の中、1971年には大川博オーナーが死去。野球を愛したオーナーが亡くなると、後任の*3岡田茂オーナーは、東映の拡大路線をとってきた大川色の一新を進めていたことならびに映画産業の斜陽化による経営不振で不採算事業の整理を行っていた関係から、フライヤーズもリストラの対象に入れました。そして1972年のシーズンオフ、フライヤーズは、東映から新興不動産業・パチンコ業で躍進著しい日拓ホームに身売りすることになります。日拓ホームの若き社長であった西村昭孝は、東急グループの総帥の五島慶太ならびに岡田オーナー共通の知人でした。
*3 岡田茂東映名誉会長
現日本映画界のドンで、戦後の娯楽産業を担った雄。1950年代には映画プロデューサーとしてその名前を馳せた。ちなみに、かつて愛人の竹久みちとともに逮捕されて話題になった岡田茂元三越社長とは、まったくの別人。
次回は、その日拓ホームのサプライズから日本ハムへの身売り、そしてフライヤーズとしてのチームカラー一掃に至るまでの軌跡を追っていきます。
第3回 その3:日拓ホーム→日本ハムへのオーナー企業の交代、そして張本放出まで(1973-1975)
前回は大川博オーナーの死去、そして東映の岡田茂新オーナーが日拓ホームにフライヤーズを売却するまでの話をしてまいりましたが、今回はその続きと、ファイターズが誕生して軌道に乗るまでの話です。
1973年からパ・リーグは、前期・後期の2シーズン制になります。ポストシーズンを増やし、イベントを作り出して盛り上げ、なんとか巨人を中心とするセ・リーグの人気に対抗しようとする苦肉の策でした。
そんな中、新たなパ・リーグのチャレンジの象徴となった若き新オーナーの西村昭孝社長は、楽天イーグルスを2004年に創設した楽天イーグルスの三木谷オーナーと同様に「必ず優勝する」と宣言し、積極的なアクションに打って出ます。西村オーナーが経営する日拓ホームは、赤坂、新宿、渋谷といった地域にて大衆相手に現金決済主義の日銭商売を行うパチンコ業や貸不動産業を営むことにより、急激に台頭してきた企業でした。
この年、フライヤーズは、前期5位に終わると田宮監督を解任。後任にはOBの土橋正幸を就任させ、西村オーナーは当時派手なカラーユニフォームが時流になりつつあったメジャーリーグの影響を受けてか、7色のユニフォームを採用して話題を呼びます。
チームとしても打力を全面に押し出す積極的な試合を行い、後期は3位になりました。投手陣はエースの金田が不調ではあったものの、主力投手が全員防御率3点台で後半盛り返し、高橋直樹もノーヒット・ノーランを記録、新美敏が新人王に選ばれました。
しかし予想外の出費の多さから、日銭商売で儲けることを企業経営ポリシーにしている西村オーナーは、長期に渡る投資への見返りを待てなかったために、次第に球団経営への意欲を失っていきます。夏には身売りの噂が流れるようになり、有力な売却先の候補として、空調設備の製造・販売会社であった日本熱学の名前が一部メディアの間で挙がってきました。日本熱学は牛田社長が野球好きで社会人野球のチームを所持していたため、買収は確実とみられ、新チーム名は日熱エアロマスターズというまことしやかな噂も流れるようになったのです。
ところが実際のところ、日本熱学は倒産寸前で、フライヤーズ買収は会社の経営状況を誤魔化すための世間へのアピールに過ぎず、結局買収はなりませんでした。そこで西村オーナーは身売り先を探しましたが、結局見つからず、最終手段としてロッテオリオンズ(現千葉ロッテマリーンズ)との合併を試みますが、合併の条件が折り合わず、これは失敗に終わります。そこで西村オーナーは球団経営の継続は無理と表明したため、パ・リーグは来期5球団での興業にせざる得ない状況に追い込まれました。すると、ただでさえセ・リーグに人気で差をつけられて興業収入が少なく、親会社の補填でかろうじて運営しているパ・リーグの各球団は、リーグの維持が困難とみて、リーグ合併話をセ・リーグに持ちかけます。しかしセ・リーグも、球団の増加は主力収入源である巨人戦の収益減になるため、承知しませんでした。ちなみにこの経緯についていえば、一説には、セ・リーグ側から「合併するなら対等合併ではなく、吸収合併で、興業の都合があるのでパ・リーグ側は、フライヤーズの他もう1球団減らして参加は4球団とし、フライヤーズともう1球団の選手の保有権はセ・リーグで管理する。選手の分配と興業権はすべてセ・リーグ球団優先とする」という無理な条件が出されたためにパ・リーグ側が承知しなかったので、1リーグ制への移行が成立しなかったとも言われています。
この結果、ファンを無視した両リーグ球団のエゴで事態は泥沼状態に陥り、次季のプロ野球興行の開催も危ぶまれてきました。そこで最終的に、巨人の実質的オーナーであった務台光雄の意向によって、正力亨オーナーの「1リーグ化によって球団数が減ることは、プロ野球興業の減収になり、その発展を阻害しかねない。パ・リーグ側でフライヤーズの売却先をなんとか確保するように努力すべきで、どうしてもだめなときは再考しよう」という声明が出されることとなり、1リーグ制への移行は消滅したのでした。そして、前ヤクルトスワローズ監督の三原脩による紹介を受けた大社義規の英断で、その大社が経営している食品製造・販売会社日本ハムによる買収が成立し、パ・リーグ消滅の危機は避けられたのです。
大社オーナーは野球王国香川の出身ということもあり、大の野球好きで、日本ハムは巨人の主催試合のテレビの全国放送の有力なスポンサーのひとつでしたが、当時は関西のローカル食品会社であり、事業の全国的な展開には強力な宣伝が必要と決断して、球団を買収したのでした。
日本ハムは、チーム名を戦う集団ファイターズに改めて新生球団としてのスタートを切り、1974シーズンからペナントレースに参加しました。前述の三原脩を球団社長とし、西鉄ライオンズの4番として鳴らし、プレイングマネジャーとしての経験もある中西太を監督に迎えてシーズンにのぞみましたが、最初の年は最下位に終わりました。
また、買収当初は企業規模が小さくて運営費用の足りなかった日本ハムは、ファイターズにカネをかけられず、ファイターズとして再出発した当初は大社オーナーの個人負担で球団運営費を補填していました。当然球団経営にはカネをかけられませんから、選手の待遇や設備は良くなりません。これは、フライヤーズのときから変わりませんでした。
一方、このファイターズがスタートした直後の5月に、フライヤーズ買収の候補だった日本熱学が倒産します。そこで、この事件を受けてある週刊誌では、「日本熱学が球団を買収していたら選手は路頭に迷うところだった。選手は野球ができるありがたさを理解して精進するべきだ。」というありがたくもない一方的な説教記事が出ましたが、フライヤーズ時代から待遇の悪さに不満があった選手たちは、
「ドラフト制度のおかげで仕方なく、フライヤーズに入団しただけ。待遇も設備も悪いし、身売りが続いて落ちついて野球をすることができない。球団名が変わっても待遇も設備も変わらない。テレビによる試合の全国中継があって、観客数が多く、経営の安定しているセ・リーグの球団に入団していればこんなことにはならなかった。我々の気持ちがわかるものか。金も出さずに無責任なことを書くな」
と反発しています。私自身いつも思うことですが、公衆に向かって意見を発するときは、相手の状況をよく見て書くことが当たり前のマナーなんであって、無責任にイージーな意見をボロッと出してしまったら相手から余計な反発を食らうだけですから、この手のことについては、慎重に書いていきたいものです。
さて、話はファイターズのカネなし状態の話に戻りますが、フライヤーズ時代後期に引き続きこのように待遇の悪い状況ですから、当然選手はやる気が出ません。そして、これら不満のある選手たちを、中西監督はまとめることができませんでした。相変わらず投手陣が不調で、人件費の削減から前年不調だったエース金田をロッテの野村収とトレードしましたが、やってきた野村はわずか4勝に終わる一方、金田は、兄・正一監督の下でやる気が出たのか16勝をあげてロッテの優勝に貢献し、MVPに選ばれています。
また一方、ファイターズは金田の抜けた穴を埋めきれませんでした。即戦力と期待してドラフト指名した鵜飼克雄が実力を発揮できなかっただけでなく、助っ人外国人のマイケル・ケキッチも期待はずれに終わり、球団の最多勝は新美の12勝でしたが、到底エースの働きには及ばなかったのです。
一方、打撃陣も張本こそ首位打者を獲得しましたが、他の選手は全員前年より成績を落としています。これでは最下位もやむをえないでしょう。
このシーズンのファイターズの明るい話題といえば、万能選手高橋博士が史上初の1試合で9つの全ポジションを守るというパフォーマンスを行ったことぐらいで、テストで採用した投手のバール・スノーが4月の給料の受け取り直後に失踪し、球団による警察への詐欺罪としての告訴によってコミッショナーから球界永久追放の処分を受けたことや、ケキッチのスキャンダラスな私生活が週刊誌に取り上げられるなどといった締まらない話がマスコミに出るばかりで、肝心の野球の話題が出ることはありませんでした。
当時は、ロッテオリオンズの金田正一監督が三塁コーチャーズボックスにて、サインの他にカネヤンダンスと呼ばれるパフォーマンスを披露しており、アストロ球団というマンガにてこれが取り上げられるほど非常に人気がありましたが、それに対抗して、中西監督が巨体を使ったパフォーマンスを披露したところで、勝てなければ効果はありませんでした。ファンからは「そんなことをする前にもっとやることがあるだろう」と非難される始末です。
このように、26年間親しまれたフライヤーズとは決別して生まれ変わったはずのファイターズではありましたが、最下位に低迷したことや、フライヤーズ時代からのファンが離れたことなどの悪条件が相まって、観客数は低迷しました。そこでこの事態の打開のため、球団は、大杉、白、大下剛史といった主力を放出し、代わりに小田義人、内田順三、東田正義、上垣内誠を獲得しています。ちなみにこの当時、トレードを進めた球団社長がかつては名将といわれた三原脩だったので、「乱暴なだけで個人プレーに走る選手を放出し、チームの体質を変えるためのトレード」とこのトレードを好意的に書いている記事が多いようですが、実際は経費節減が第一目的であり、同時にフライヤーズカラーを一掃することをも狙って、トレードは行われたのでした。これは、年俸高騰による主力選手の放出や買収前のチームカラーの一掃といった名目でチームが培ってきたものを簡単に切り捨ててしまうという企業野球のひずみがまたしても出た例であり、多くのパ・リーグの球団がたどってきた道でもあったのです。
したがってこのトレードをきっかけに、フライヤーズ時代のファンはますますファイターズから離れていくことになってしまいました。そこでファイターズは観客動員を促す努力のひとつとして、他球団に先駆け、新規少年ファンの開拓を目的として「少年ファイターズ友の会」を発足させ、今日に至っています。いまでこそすっかりポピュラーになった感のある少年ファン獲得のためのこのシステムも、先鞭をつけたのはファイターズだったのです。もっとも当時、少年ファンの間で圧倒的に人気があったのは巨人で、少年ファイターズの会に入っていた子供は全体のごくごくわずか、しかも彼らは、安くチケットが手に入るといった理由で入っていたことが多く、純粋なファンではなかったことが多かったのですが...
さて、このように経費節減のため、ドラフトで新人の大物選手も指名できず、主力選手を次々と放出せざるを得ない状況にあったファイターズは、次第に地味なチームとなっていきました。
1975シーズンは、移籍でようやく実力を発揮した小田が、首位打者のタイトルを、太平洋クラブライオンズに移籍したトレード相手の白と最後まで争い、大学の同期生千藤三樹夫とともに、主力として定着しました。同じく移籍の内田も、いい成績こそあげました。
しかしながら両者をもってしても、移籍した大杉、白の穴は埋めることはできなかったのです。いくら個人成績がよくてもチームに完全に溶け込んだわけではなかったので、いまひとつ決定力不足だったのでした。また、助っ人外人のジェスター・ゲーリーも日本ハムのコマーシャルに出演してファンにアピールしましたが、期待はずれで、主砲の張本の不調のこともあり、さらに得点力は下がってしまったのです。
投手陣は、高橋直樹が17勝をあげエースとなりましたが、他は不調を脱した野村が11勝あげただけで、前年に続くチーム力不足により、2年連続最下位に終わりました。
そこでファイターズは、不振の成績を負わせて中西監督を解雇。後任には、南海(現ソフトバンクホークス)、東京(千葉ロッテマリーンズ)の外野手で、1971シーズン途中から1972シーズンまでロッテ(現・千葉ロッテマリーンズ)の監督を務めた大沢啓二が就任しました。いまでもマスターズリーグの会長として君臨し、大沢親分と呼ばれて球界では有名人でありますが、一度挫折したあの人の監督人生は、ここから再びはじまったのです。
新たな監督に就任した大沢は、経費節減を兼ねたチームの体質改善をさらにすすめ、またもや大型トレードを実行します。
主力選手の坂本敏三、東田正義、渡辺秀武をはじめ、ついに至宝の張本も放出。このトレードは得点力低下に悩む巨人からの強い要望もあったのですが、75年のシーズン打率が三割を切り、高年俸と35歳の年齢からくる衰えからこれ以上の成績が望めない、と球団で判断した結果でした。2006年10月現在、TBS系列の朝の番組に出ているこの2人のツーショットというのは、この経緯を考えると、なんと皮肉なものであろうかと考えさせられるところではあるのですが...
そしてファイターズはさらに、トレードで永渕洋三、富田勝、高橋一三を獲得しましたが、その結果生え抜きの主力は投手の高橋直樹の他、野手は千藤ひとりになりました。最後の看板選手張本の放出で、ファイターズはさらに地味なチームになってしまったのです。これでフライヤーズ時代からのファンはますます離れてしまいました。また、移籍選手がチームの主流を占めたため、ファイターズの誰を応援してよいか迷うファンが大半となってしまい、観客数は低迷したままだったのです。後楽園球場では閑古鳥が鳴き、同じ後楽園を本拠とする長嶋監督の巨人とは、大きな差がついてしまいました。
ここからファイターズがどのように変貌して、現在に至るのかについては、次回のこのシリーズの最終回にて語ることといたします。
第4回 その4:新生ファイターズによる再出発、初の後楽園日本シリーズ、そして現在に至るまで(1975-2006)
前回は日拓ホームのフライヤーズ買収、1年での売却と日本プロ野球の1リーグ化の危機、そして日本ハムによる買収とチーム名のファイターズへの変更の話をしましたが、今回はその後のファイターズの変貌、そして現在に至るまでの話です。
1976シーズン、打撃陣は移籍により復調した富田が1番を打ち、張本とゲーリーの代わりに補強した助っ人外人ワイラー・ウィリアムスとボブ・ミッチェルがふたりで46本塁打を放った上に移籍の永渕も健闘したので、得点力は上がりました。しかしチームとしては、いまひとつ決定力を欠いたままでした。また投手陣は、高橋直樹、野村に加え、移籍の高橋一三が二桁勝利を上げましたが、それ以外の投手は成績があがらず、上位を狙うには力不足で、結局チームは5位に終わりました。たまたま太平洋クラブライオンズが運営資金の不足による待遇の悪化で最下位になったため、最下位だった前年とチーム力はほとんど変わらなかったといえます。高年俸選手の整理とフライヤーズカラーの一掃はほぼ終わりましたが、相変わらず補強費用が不足していることには変わりません。
またこの年のドラフトでは、苦労を重ねます。まず、ファイターズになってからは初の全国的に知名度ある選手として、春の選抜高校野球大会の優勝投手である崇徳高校の黒田真二投手を1位で指名しましたが、黒田投手は地元・広島東洋カープの入団を熱望していたこともあり、「肉は好きだけどハムはきらい」という発言を残して入団を拒否。さらに、ファイターズが1位で黒田投手を指名したことでプライドを傷つけられたのか、2位指名の藤沢公也選手からも「高校生より自分の評価が低いのか」と入団を拒否されてしまいます。そしてこのようなゴタゴタが続いた結果、ファイターズは、アマチュア選手から指名して欲しくない不人気球団のひとつになってしまいました。
しかし、この年のドラフトでは上位指名こそ不発に終わりましたが、4位ではのちの名キャッチャー、大宮龍男を指名、さらにドラフト外では島田誠、岡部憲章などといった、後の主力選手が入団させています。このようにファイターズは少しずつ、戦う集団へと変貌する準備を整えていったのです。
明けて1977シーズン、投手陣は高橋直樹が17勝をあげ、復調した村上雅則が抑え投手に定着しましたが、他に二桁勝利をあげた投手は不在でした。一方打撃陣は、日本の野球に慣れたミッチェルが32本塁打と長打力を発揮し、加藤俊夫が捕手のベストナインに選ばれましたが、新戦力の台頭はなく、決定力不足も相変わらずで、5位に終わりました。
そしてこの年のシーズンオフには、のちのファイターズの命運を変える事件が起こります。それは南海ホークスでの野村監督解任騒動でした。ホークス後援会副会長の娘である夫人との別居、ならびに愛人(現・沙知代夫人)との事実婚、そしてその愛人による現場への介入疑惑が発覚し、これを機に、野村監督就任後冷遇されていた*4鶴岡一人元ホークス監督時代の選手や球団スタッフが逆襲したため、川勝傳ホークスオーナーもついにかばいきれなくなり、野村監督は解任され、関西からは叩き出されるという形になります。
*4 鶴岡一人
近畿グレートリンクの時代から南海ホークスの監督を23シーズン務めた名将。親分と言われ、多くの選手から慕われていた。野村を捕手として見いだした監督でもある。野村は、鶴岡の取った人情野球を否定し、ドン・ブレイザーから吸収した合理的なデータ野球を断行、鶴岡時代の選手・球団スタッフをチームから遠ざけていたために彼らが反発しており、この解任は、鶴岡派の逆襲と言われた。なお、鶴岡は解任に関する関与を否定したが、野村は、解任は鶴岡の意向と信じており、鶴岡の葬儀にも出席しなかった。この事件の真相は不明であり、さまざまな説があるが、野村が関西から閉め出されたのは、鶴岡に遠慮した関西マスコミの報道姿勢の結果であり、鶴岡は直接関与していないと言われている。
するとその騒動の影響で、野村監督の解任に反発した柏原純一選手がホークスからの放出を希望してフロントと大喧嘩になり、紛糾。そこでファイターズはトレードを申し入れ、小田義人選手と杉田久雄投手との交換で、柏原選手の獲得に成功します。これは移籍後の柏原選手が実力を発揮して4番に座っただけでなく、後にオールスターでパ・リーグの4番も務めたことを考えると、大成功のトレードでした。打撃陣に軸になる選手が不在だったファイターズにとって、何よりも欲しい選手が入団したのです。またこの年は、ドラフトで、のちのファイターズのクリーンナップに名を連ねることになる古屋英夫、田村藤夫を獲得しています。このように地味ながら選手の補強が着々と進行すると同時に大沢監督の指導も徐々に浸透してきて、ファイターズのチームカラーは次第に確立していったのでした。
続く1978シーズン、打撃陣は、俊足の島田誠が1番を打ち、2番富田がクリーンアップに繋ぎ、打撃好調の4番・柏原、5番・ミッチェルが打点を挙げるというパターンが確立したので、前年よりも得点力が上がりました。またこのシーズンは、柏原が24本塁打84打点でベストナインに選ばれ、ミッチェルが36本塁打で本塁打王を獲得しています。
さらに、力をつけてきた管野光夫と新人の古屋がレギュラーに定着し、下位を打つベテラン千藤、加藤も健在で、ファイターズはようやくファンにアピール出来るようになりました。
投手陣は、エース高橋直樹と高橋一三が不調でしたが、移籍組の佐伯和司、押さえ投手の村上がそろって二桁勝利をあげ、大洋に放出した野村の替わりに移籍してきた杉山知隆、間柴茂有がふたりで16勝をあげる健闘ぶりで、ついにファイターズは3位となり、初のAクラス確保に成功。ちなみにこの年のオールスターのファン投票では、高橋直樹、加藤、柏原、富田、千藤、管野、古屋の7選手が選ばれていますが、実は、これはファイターズ友の会や会社ぐるみの組織票によるものだったため、実力不足ということで管野と古屋は出場を辞退するという状況になっています。この節操なき組織票のあり方は世間から大きく非難を浴びましたが、これは、予算のない中でチームをなんとか全国にアピールしたい、という球団の熱意の表れでもありました。同じ組織票のあり方でも、なんとも涙ぐましい努力のあり方といえます。
1979シーズンは前年と戦力があまり変わりませんでしたが、打撃陣でミッチェルに衰えが見えるようになってきました。元々確実性に欠けるところがあり、彼の最大の武器であった長打力が落ちてきたことから、球団はミッチェルに代わる助っ人外国人選手探しを考えるようになったのです。他は、新人の高代延博がレギュラーに定着しています。
投手陣は、復調したエース高橋直樹が初の20勝。杉山、佐伯も二桁勝利で、宇田東植も9勝をあげ、次第に安定してきました。
その結果このシーズンも3位を確保し、前年の成績がまぐれでないことを証明しています。
またこの年のシーズンオフには、社会人野球界から木田勇をドラフトで獲得。ファイターズになってからは初めての、大物アマチュア選手の獲得でした。さらにミッチェルを解雇し、新しい助っ人外国人選手として、トニー・ソレイタ、トミー・クルーズを獲得しています。
1980シーズン、投手陣では、新人木田の活躍が目立ちました。シーズンを通して22勝8敗の成績を残し、池永正明(西鉄)以来の新人20勝到達を始め、投手5冠を独占。ファイターズ史上初のMVPを獲得しましたが、これはチーム通算としても、フライヤーズ時代の張本以来のことでした。また木田は、尾崎行雄以来のピッチャーのベストナインにも選ばれています。したがってこの年は、シーズン中からオフまで木田の話題で持ちきりでした。
しかし、木田の他は高橋直樹と間柴が二桁勝利、復調した高橋一三が9勝をあげたものの、抑えの村上の不調で終盤での競った戦いを落とすことが多かったために追い込みができず、3位に終わりました。そこで球団は、村上に代わる抑え投手の補強を決断しています。
一方打撃陣は、島田と新外人のクルーズが三割を打ちましたが、なんといっても「サモアの怪人」ソレイタの活躍が目立ちました。確実性に欠けるきらいはありましたが、ミッチェルの長打力を上回る45本塁打、95打点を記録し、明るい性格のこともあって、一試合4打席連続本塁打を打った翌日のスポーツ新聞には「ソレイタ!おソレイっタ」と見出しが出るなほどの人気選手となりました。
また、地味ながら高代が、ファイターズに入団した野手として初めてベストナインに選ばれています。
このように、木田とソレイタの活躍によって、ファイターズはパ・リーグの上位球団の仲間入りを果たし、優勝も夢ではなくなりました。
そしてこの1980シーズンのオフ、ファイターズは、広島カープの抑えの切り札である江夏豊を、高橋直樹とのトレードで獲得します。抑えの不在に泣かされたファイターズにとって、広島で二年連続日本一の抑え投手の獲得は、大きな戦力アップになりました。
すると翌1981シーズンは、木田が二年目のジンクスで調子を落としたために10勝に留まったのは計算外だったものの、投手陣のほかの面子では、調子をあげた間柴が15勝、高橋一三が14勝をあげ、次いで急成長した岡部が13勝をあげています。また、抑えの江夏の存在は大きく、3勝25セーブを記録しました。
打撃陣は、1番島田、2番高代がクリーンナップのクルーズ、柏原、ソレイタに繋ぐ野球で得点力が上がりました。下位を打つ古屋、中日に放出した富田の替わりに入団した井上弘昭、村井の他、控えの管野、鍵谷、岡持、服部も活躍し、成長してレギュラーになった捕手の大宮が投手陣を引っ張ります。
この結果ファイターズは後期優勝し、プレーオフで山内一弘監督率いるロッテオリオンズを破って、待望の日本シリーズの出場を決めました。ファイターズになってから7年目の快挙であり、私財を投げ打ってまでファイターズを運営することに邁進してきた大社オーナーは、大泣きして優勝を喜んでいます。フライヤーズ時代の選手は、岡持と加藤のふたりだけ。移籍選手中心の寄り合い所帯を巧みにまとめた大沢監督の手腕が光りました。そしてフライヤーズ時代からは19年ぶりのシリーズ出場でしたが、この年のセ・リーグの優勝は巨人。両チームとも後楽園を本拠地としており、史上初の移動のないシリーズが実現。旧フライヤーズ時代のファン待望の東京シリーズは、ついに現実のものとなったのです。
ファイターズは、初戦で巨人のエース江川卓と抑えの角三男を崩して先勝し、第3戦までは2勝1敗と勝ちが先行しましたが、第4戦の後半に守備の乱れから崩れて大敗すると、第5戦では第2戦に続く西本聖の力投に敗れ、第6戦では西本の活躍に奮起した江川の投球の前に打線が沈黙、試合の前半の時点で巨人の新人原辰徳の2点本塁打を含む5点を奪われ、その後は井上の本塁打などで追いすがりましたが、結局6対3で敗れ、通算2勝4敗となり、日本一はなりませんでした。
しかしこの年、リーグ最優秀選手には江夏豊が選ばれ、また、島田と柏原がベストナインに選ばれています。
以後、ファイターズは日本シリーズに出場することなく、2004年に本拠地を北海道に移転しています。一度優勝はしましたが観客が入らず、後楽園に続いて本拠地にした東京ドームではドリンクを販売するときに氷を抜いたり、年間シートを格安で販売するなどの努力を重ねていましたが、いくらそういう企業努力をしたところで、外野席は埋まっても内野席で閑古鳥が鳴いていては、収支が合いません。たくさんの観客が入ってこそ球団の収支は見合うわけですから、この移転は、東京を出てそのチャンスを北海道に求めようという、フロントの大きな決断でした。そして人気者の新庄剛士を獲得、アメリカの3Aで将来のメジャーリーグの名監督候補と言われたトレイ・ヒルマンを監督に招聘、北海道にフランチャイズを置く初のプロ球団としてのスタートを切ります。
そして大社オーナーは晩年、日本ハム株式会社の補助金不正取得事件発生の関係からオーナー職を辞し、失意のうちに亡くなりますが、そんな事件の最中でも着々と力をつけてきたファイターズはヒルマン監督の下、低迷を脱して上位に進出し、優勝をねらえるチームへと再び変貌しました。ファイターズを運営する会社も、日本ハム資本100%の会社から、北海道の地元企業の資本を入れた会社へと代わり、オーナーも大社オーナーの息子さんへと交代。いままさに新たな強豪チームとしてパ・リーグに名乗り出た北海道日本ハムファイターズの戦いは、これからも続くのです。
【参考文献】
・プロ野球人名辞典2003 森岡浩編集
・プロ野球データ辞典 坂本邦夫
・別冊週刊ベースボール プロ野球新・トレード史
日本シリーズの軌跡
戦後プロ野球五十年、背番号の人生、プロ野球比較選手論
・プロ野球トレード光と陰 近藤唯之著