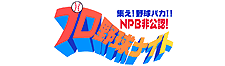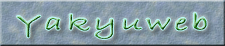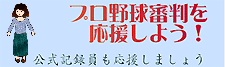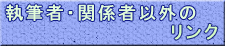ニグロリーグと愉快な仲間たち by MB Da Kidd
第1回 ニグロリーガーの来日〜その1〜
こんにちはMB Da Kiddです。
残念ながらShinorarさんのリクエストどおりにはいきませんで、僕がジャップ・ミカドこと三上吾郎さんのことについて書き出しますと、全部で5回ぐらいに分けて書くことになっちゃうので、今日はそのネタをひっこめときます。
いつかやりたいとは思ってますが、おいしいネタは冬にまた、ということで(^^)
今日は、ニグロリーガーが日本に来たときの話その1です。
● メジャーリーグ・オールスターチームと同時期に来日
メジャーリーグ・オールスターチームを1931年に読売新聞社が社運をかけて招待したことは有名ですが、ニグロリーガーたちはそれよりも前、1927年に来日しています。
そもそも日本がアメリカのチームを招待して興行を行った歴史は古く、1907年にはハワイ・セントルイスチーム、1908年には初のプロ野球チームであるリーチ・オール・アメリカンが来日しています。
ちなみに1907年のセントルイスチームの興行は、日本初の有料試合です(脱線失礼)。
リーチ・オール・アメリカンは3Aクラスの選手とメジャー級選手の混成チームですから、メジャーリーグ・オールスターズと実力的には大分迫っていたのかもしれませんが、オールメジャーということになりますと、1913年の世界周遊野球チーム(シカゴ・ホワイトソックスとNYジャイアンツの混成チーム。NYジャイアンツはいまのSFジャイアンツです)まで待たねばなりませんし、またメジャー選抜ということになりますと、さらに1922年まで待たねばなりません。
が、戦前日本に来た最強のチームということになりますと、やはりこの1927年のニグロリーガー中心に編成された、フィラデルフィア・ロイヤル・ジャイアンツということになるのではないか、というのが私の考えです。
というのも彼らは、主力がニグロリーグのマイナーレベルであったとはいえ、ニグロリーグの若手と経験豊富なベテランがうまい具合に混成されたチームで、短期決戦をやったり興行を行っていく上では、最適な人員構成になっていたからです。それに加え、1923年にルーブ・フォスター・コミッショナーによって創始されたニグロリーグでは当時、ベーブ・ルースのつむぎ出す”ホームランの夢”の影響によってメジャーリーグでは廃れだした”スピード&チャージ”のタイ・カッブ以来の伝統が、フォスターコミッショナーの影響もあり、脈々と受け継がれていたこともあって、アフリカン・アメリカン生来のパワーに加え、タイ・カッブの影響を受けた”スピード+細かさ”を組み合わせた、世界最強の野球が展開されていたのです。その証拠に、白人メジャーリーガーの在籍するチームとニグロリーガーが在籍するチームとの対戦では、通算では184勝84敗という成績が残っています。無論、100も勝ち越しているのは、ニグロリーガーたちが在籍したチームの方です。
しかし、彼らは招待されたわけでなく、自前でチームを編成し、日本に興行にやってきたということだったので、結局球史の中ではマイナーな存在になってしまったのです。
● 巡業野球チームという存在
当時のアメリカでは、野球選手の社会的地位は相対的に低いものでした。したがってメジャーリーガーですら巡業野球チームを編成して、シーズンオフを利用して一稼ぎすることは珍しくなかったし、また、白人選手に比べて稼ぎが悪かったのではないかと推測される彼ら黒人選手にとって、巡業は生活に直結する死活問題だったでしょう。
ニグロリーガーたちの足跡は実に広く、当時メジャーリーグチームがなかった西海岸だけでなく、カリブ海諸国にまで行って巡業を行ったり、キューバの大統領の前でプレイしたりしています。
余談ですが、このときの彼らの巡業が、いまのドミニカやキューバ、プエルトリコといった国や地域の野球熱のもとになり、いま大活躍中の数々の名選手を生む土壌を育てたといえます。
そして彼らは、ついにその足を日本にまで伸ばしてきたのです。
彼らが日本でやったことについては次回取り上げますが、簡単にまとめますと、彼らの日本球界になした貢献は、カリブ・中米諸国に彼らがなしたことと同じものでした。
● 記録はちゃんと残っている
コミッショナー事務局が出している『オフィシャル・ベースボール・ガイド』によりますと、
▼1927年(昭和2年)
黒人ローヤル・ジャイアンツ 24試合 23勝1分
▼1932年(昭和7年)
黒人ローヤル・ジャイアンツ 24試合 23勝1敗
という記録があります。
彼らは確かに、日本に足跡を残していました。
ちょっとこの話については面白いエピソードがたくさんあるので、今日はここまで。次回は、日本で実際に彼らがやったことの数々についてです。
(2004.6.11.配信)
第2回 ニグロリーガーの来日〜その2〜
こんにちはMB Da Kiddです。
ちょっと球界の騒動について、Shinorarさんはこのやきゅうの手帳にて、ワタクシはぼーる通信にて手分けして特集を組んでいたために、すっかり遅れてしまいました。
しかし皮肉なものです。自分としては数年前から、いずれ日本プロ野球は21世紀のニグロリーグになるぞ、ニグロリーグのように時代の波に呑み込まれてしまうぞ、とずっと警告してきたのですが、それがこんなに早く来るということは、まったく考えていませんでした。
ニグロリーグがどうしてなくなってしまったのかということについてはそのうちに突っ込んで書かせていただこうと思っていますが、何かが消えるというのはさびしいことです。
ただ、何かが歴史に残ると、それは未来へとつながっていきます。このニグロリーグは日本にだけでなく、カリブ海諸国へも大きな影響を残しています。キューバ、ドミニカ、プエルトリコといった国や地域は多数のメジャーリーガーを輩出していますが、これら出身のメジャーリーガーはいずれも、ニグロリーガーの末裔なのです。
そして今日は、日本に彼らが残した遺伝子についてのお話、第2回です。
● 1927年の面子
前回、『オフィシャル・ベースボール・ガイド』によれば
▼1927年(昭和2年)
黒人ローヤル・ジャイアンツ 24試合 23勝1分
▼1932年(昭和7年)
黒人ローヤル・ジャイアンツ 24試合 23勝1敗
という記録があるという話をしました。今日はそのうち、1927年来日時のメンバーの話です。
このときの面子は全部で14人。ニグロリーグを代表するキャッチャー兼ショートのローリー(ビズ)・マッキーをはじめ、ハーバート(ラップ)・ディクソンといった名選手を中心に構成された巡業チームでした。
その中でも特筆すべきなのはビズことローリー・マッキーです。彼はキャッチャー、ショートを主にやり、その強肩から繰り出される球は『スナップスロー』と呼ばれ、座ったままノーバウンドで強烈な送球ができるほどでした。
バッティングはスイッチヒッターとして巧打を披露。1923シーズンには.362という高いアベレージを残し、首位打者にも輝いています。
ニグロリーグのオールスターでは、のちに紹介させていただくことになる、962本の球界最高通算本塁打数を誇るジョシュア・ギブソンや、俊足豪打で鳴らしたオスカー・チャールストンらとクリーンナップを組むほどでした。
この堅守と巧打を誇るビズは、現代でいえば、同じく堅守と巧打を誇るイヴァン・ロドリゲス(現デトロイト・タイガース)のような名選手だったのです。
また、ラップ・ディクソンは、この日本遠征の後、急速に成長し、功成り名を遂げた選手です。
パワー・スピード・巧打を兼ね備え、驚くほどの強肩とアグレッシヴなプレイで、ニグロリーグに来ていた観客を魅了しました。
彼のハイライトは、ヤンキースタジアムにおけるニグロリーグ初の試合です。
NYリンカーン・ジャイアンツとボルティモア・ブラックソックスとの間で行われたこの試合にて、ディクソンは左打席から3発をライトスタンドに叩き込み、20,000人の観客を興奮の坩堝に巻き込みました。
のちにピッツバーグ・クロフォーズというニグロリーグ版NYヤンキースのようなオールスターチームに加入し、上記のジョシュア・ギブソンやオスカー・チャールストン、ならびに、シーズン175盗塁という驚異的な記録を残している球史上最速男、クール・パパ・ベルらとともに打順に名を連ね、.343、15本塁打という好成績を残しています。
現代でいえば、全盛期のケニー・ロフトン(現NYヤンキース)といったところでしょうか。ディクソンのプロファイルを読んだとき、私は1995年のボールパーク・イン・アーリントンにおけるオールスターゲームにて活躍したロフトンのことを思い出しました。
(shinorarより補足:1995年のオールスターでは、近鉄からLAドジャースへ移籍したHIDEO NOMOが先発登板し、先頭打者ロフトンを空振り三振に仕留めましたとさ。)
● 日本で彼らが残した足跡
ジャパン・タイムズ・アンド・メイル(現ジャパンタイムズ)紙によれば、彼らは3月30日に日本に到着しています。
カリフォルニアでのウィンター・リーグに出ていたときの好調さを維持しつつ、来日したようです。
ですが、彼らは長旅のつかれを癒す間もなく、2日後には当時日本でも最強だったチームのひとつ、三田クラブ(オール慶應)と対戦しています。
そんな彼らは、特筆すべき記録を残しています。
・ビズ・マッキーの神宮球場初ホームラン
・ラップ・ディクソンの甲子園史上最長長打
次回は、これらについて、当時の神宮球場や甲子園の事情も含め、お話します。
(2004.7.29.配信)
【参考図書・web】
黒きやさしきジャイアンツ 佐山和夫著 ベースボールマガジン社
Negro League Baseball Player Association - Raleigh(Biz) Mackey
Baseballlibrary.com - Rap Dixon
第3回 ニグロリーガーの来日〜その3〜
こんにちはMB Da Kiddです。
渡邊恒雄という人が急にいなくなってしまい、何だかよくわかんない状態になっている日本の球界ですが、やはり、企業の事情によって勝手にチームをなくしたり、移転させたりするとファンのみなさんからの反発が大きいのは当然で、いまの日本の球界を見ていると、そのことについての認識がまだまだ球界関係者の間でも甘いな、と思わされることが多いです。
一方で学生野球は、見ててずいぶん楽しくなりました。ここ10年で大分指導者のみなさんの意識が変わってきたように思います。実際お話していても非常に拓かれた考えの持ち主の方々が多いですし、彼らにはまだまだ未来があるんだなって思います。いま高校球児の数も、過去最高の16万人ですしね。
さて、時は遡って1920年代。まだその学生野球の人気がいま以上に絶大で、プロの胎動期であるこの時代、ビズ・マッキーをキャプテンとするニグロリーガーたちが何をやっていたのかというお話、今日はその第3回です。
彼らが当時竣工したばかりの神宮球場や甲子園球場で、果たしてどんなどでかいことをやってのけたのかという話をいたしましょう。
● 神宮球場第1号本塁打
学生野球、特に六大学を中心とした大学野球のメッカである神宮球場が編纂(へんさん)した資料に、『半世紀を迎えた栄光の神宮球場』という冊子があります。
その冊子をぱらぱらとめくると、この球場が竣工した1926年の翌年、神宮球場で初本塁打が出たことについての記述があります。
『昭和2年、慶大宮武初の本塁打。
天長節の4月29日、慶帝(※2)1回戦において、慶大宮武選手は8回、帝大東投手の投じた1-0後の球を左中間スタンドに叩き込み、六大学リーグ戦、神宮球場における初の本塁打を記録した。
それより先、4月に来日したロイヤル・ジャイアンツ(黒人職業チーム)のマッキー選手が、4月20日、神宮球場で本塁打を放っている。これは外人の第1号本塁打であるが、日本人としては宮武が第1号本塁打の記録保持者である』
当時の神宮球場とは、どれほどの大きさだったのでしょうか?神宮球場の公式HPによれば、以下のデータがあります。
・両翼100m、中堅118m
・スタンド観客席9,000人、芝生観客席22,000人
これは、いま現在のヤンキー・スタジアムよりも両翼がひろい(ヤンキースタジアムはそれぞれ、右翼が95.77m、左翼が96.99m)というでかさです。また、この時代、いまよりもはるかに質の悪い、飛ばないボールを使っていたことを考えると、マッキーのなしたことがとんでもないことだということがわかっていただけますでしょうか。しかも彼は、4月25日、4月28日と第2号、第3号ホームランも放っております。
これは、マッキーのとてつもないパワーを示している出来事です。
以前にボブ・ホーナーが現役バリバリのメジャーリーガーとしてスワローズに入団し、いきなりホームランを連発して赤鬼といわれ、怖れられたことをご記憶の方もいらっしゃるやもしれませんが、マッキーのパワーはそれを上回っているのではないか、というのが私の持論です。飛ばないボール、そしていまの神宮球場の両翼91mという狭さを考えると(代わりに中堅は120mと2mほど広くなってはいますが)、マッキーのなした偉業は、バリー・ボンズが2002年の日米野球でホームランを連発した以上のインパクトがあったのではないでしょうか。私たちはバリーのものすごいバッティングを衛星放送で見ているからわかっていますが、映像でマッキーを見たことがなかったはずの明治時代の野球好きのみなさんがマッキーの豪打に驚いたことは、決して想像に難くありません。
● 甲子園球場初長打
さて、今度は舞台を日本のリグレー・フィールドともいえる甲子園へと移しましょう。ここでは、前回に当時のケニー・ロフトンではないかと紹介したラップ・ディクソン選手が、どでかい当たりを放ちました。このことにつき、報知新聞社の『プロ野球25年』から引用してみましょう。
『当時の甲子園球場は、中堅の最も近いところでも417フィート(約127メートル)もあり、一人として見物席に打ち込んだ者はなかったが、中堅壁に直接当てたものは、昭和2年のディクソン(4月6日、対大毎・投手渡辺)と、同4年カリフォルニア大学のリクセン(6月10日、対慶大・投手上野)の2人の名が記録されていたが、昭和6年大リーグ選抜チームのシンナースは対早大の試合に伊達投手の球を、またシモンズ(※4)が対慶応の試合に上野投手の球を直接壁に打ちつけて、名前と日付けをその打ちつけた場所に記録される名誉と、金百円の賞金を得た。この壁は昭和11年、外野席改造により、前方に出た現在のものとなったために消滅した。』
すごいですね。当時の甲子園はそんなに広かったのか、ということにまず驚きます。そこで、本家のリグレー・フィールドの改装前のデータと比較してみますと、左翼100m、右翼98m、中堅134.2mで、ちょこっとこれより狭いぐらいでしょうか。もっとも、現在の甲子園は、両翼96m、中堅120mで、改装によって小さくなってますが...
また、当時のボールが飛ばないボールであったことを思い起こしてみてください。いかに彼らが化け物のようなパワーを見せつけたかということをわかっていただけでしょうか。
しかしこの彼ら、話はやきゅうの手帳2004年6/11号の第1回に戻るのですが、やはりマイナーな存在であったことは否めません。そこで彼らがどう興行を工夫したのか、次回はその涙ぐましい努力について、佐山和夫さんの唱えた説を中心に考察してみたいと思います。
(2004.8.19.配信)
【参考図書・web】
・黒きやさしきジャイアンツ 佐山和夫著 ベースボールマガジン社
・Take Me Out To The Ballpark by Josh Leventhal BD & L
・明治神宮野球場公式ページ
・阪神甲子園球場公式ページ
第4回 ニグロリーガーの来日〜その4〜
こんにちはMB Da Kiddです。
ついに選手がストライキをぶちました。あまりに遅きに失した感はありますが、彼らができることといったら、これと契約更改の一斉拒否ぐらいしかありません。
そもそも日本のプロ野球界というのはよくわかりません。田中真紀子元外相がかつて外務省のことを伏魔伝と呼んだのは有名な話ですが、わが盟友のB_windさんはこれを20世紀の魔界と呼びました。実にうまい呼び方ですね。思わず私は笑ってしまいましたよ。
根来コミッショナーも辞任を発表しました。『理屈の通らない感情の世界にいるのはイヤ』なんだそうです。いちおう次が見つかるまでは、現職にとどまるそうですが。
しかしこんな状況を見ていると、日本のプロ野球がもしも文字どおり、21世紀のニグロリーグとなってしまうのだとしたら、実に贅沢な理由で潰れていくんだなぁという気がしますね。ニグロリーグが潰れていったのは、経営者が無能だったとか、やる気がなかっただとかいう理由ではない。アメリカ黒人、アフリカン・アメリカンの社会的地位の向上という社会的な理由が大きく密接にからんでいたのと、経営媒体が弱小だったということがあるわけです。これについてはのちほど、初代コミッショナーのアンドルー・フォスターや、強豪チーム、ホームステッド・グレイズのオーナーのカム・ポージー、そして、ピッツバーグ・クロフォーズのオーナー、ガス・グリーンリーについての考察とともにこの連載の中でお届けしてまいりますが、それは日本のプロ野球と比べても、熾烈な自由競争があったわけです。
アメリカのスーパーリッチたちのすさまじさと比べ、日本の経済界は何とノンビリしたいい世界なのでしょう。私はそれを最近、痛切に感じることが多いのです。
そして今日は、そんなニグロリーグにいた彼らが、スト中に日本プロ野球選手会のやっていたサイン会やイベントよろしく、日本に巡業中のフィラデルフィア・ロイヤル・ジャイアンツの盛り上げのために何をやっていたのかというお話です。
● 多い白熱した試合
さて、ニグロリーグの面々が圧倒的な実力を持っているということは、のちのメジャーリーガーと彼らの対戦、あるいはサッチェル・ペイジという史上最高とされるピッチャーの実力や、非公式ながら通算962ホーマーを放っているジョシュ・ギブソンといった過去の名選手のことを引き合いに出すまでもないのですが(それぞれ、のちの連載にて取り上げます)、来日したニグロリーガーたちのチーム、フィラデルフィア・ロイヤル・ジャイアンツに対し、日本で対戦したチームは圧倒的に負けてはいますが、意外にいい内容で試合をやっています。それについて振り返ってみましょう。
フィラデルフィア・ロイヤル・ジャイアンツの成績は以下のとおりです。
1927年 23勝1分 1932年 23勝1敗
ですが、当時の日本の中の強豪チームであった三田クラブ(オール慶應)、ダイヤモンド・クラブ(慶應・明治OB)、大毎クラブ、宝塚クラブ(宝塚運動協会)に対しては、1927年の来日時に、以下のようなスコアを残しています。
・対三田クラブ@外苑球場
1927.4.1. 三0-2ロ
1927.4.2. 三6-10ロ
・対ダイヤモンド・クラブ
1927.4.3. ダ7-2ロ@甲子園球場
1927.4.10. ダ2-4ロ@京都岡崎球場
・対大毎クラブ@甲子園球場
1927.4.5. 大1-0ロ(のちに1-1と修正)
1927.4.6. 大2-10ロ(前回ご紹介したディクソンの記録的長打が生まれる)
・対宝塚クラブ@甲子園球場
1927.4.11 宝3-4ロ
このようにスコア的にはかなり盛り上がるゲームをやっておりますが、特に大毎クラブ相手の1-0での敗戦では(のちに1-1の同点引き分けに訂正)、こんなことがあったと、当時ダイヤモンド・クラブでプレーされていた小柴重吉さんは語っております。
『<ダブル・プレーだから無得点>とする審判の言葉に、彼らは決して強く抗議しないのです。最初は一瞬けげんな顔をしてはいましたがね、すぐにその判定を受け入れているのです。「あなた方がそう判断されたのだったら、それに従うよ」って調子で...。私たちの方がむしろビックリしましたね。
いや、実際にアンパイヤの富樫君にその誤審を指摘する者も日本チームにはいましたがね、彼の考えは変わらない。そのうち、黒人選手の方がもう守備に走っていましてね。「いいよ、いいよ。それでいいよ』っていいましてね。あんなチーム、あとにも先にも他に出会ったことはありません。試合結果はのちに1対1の引き分けと訂正されているはずですよ』
これは実にノンビリしていて、その直後の1931年に来日していたメジャーのオールスターチームとは対照的な態度だったといえます。
メジャーのオールスターチームは『野球を教えてやるのだ』という『指南役』としての意識が高く、プライドが行き過ぎて、雨の日にはベーブ・ルースが傘をさしてゴム長靴をはきながら守備位置についたり、ラビット・モランビルが打者に背を向けてショートを守り、股間から顔を出して『ヘイ、カモーン』と日本側のバッターに呼びかけるなど、日本の野球選手を多少なりとも愚弄するところがあったわけですが、ロイヤル・ジャイアンツの面々の態度はこれとは実に対照的で、非常に爽やかなところがありました。
もちろん彼らとて、アトラクションとして遠投を見せたり、練習のときにはキャッチャーのオニール・プレンが腰を下ろしたままで2塁に矢のような送球をしたりしているわけですが、試合中はマジメで、相手を愚弄するようなことはせず、教科書のように正確なプレイをしたのです。
同じダイヤモンド・クラブで小柴さんとともにプレイした島津保雄さんはこう語ります。
『彼らのうちの何人かと直接話をしましたがね、彼らもいうのですよ。「自分たちは黒人だから、白人ばかりの大リーグには入れない。しかし、大リーガーとの試合で、対等か、それ以上の成績を残している」とね。
それほどのチームと対戦して、日本の私たちが<あと一歩>というゲームができた。敗戦を残念に思うと同時に、自信をも持つことができた。
ただ、いまになって思うことがある。
そういってしまってはおしまいですがね。彼らはいかにもプロフェッショナル。ゲームを面白く”作って”いたのではないかと...』
● 彼らが『試合を作った』背景
この島津さんの言葉はある意味、素朴な疑問を呼び起こします。
何ゆえにこのフィラデルフィア・ロイヤル・ジャイアンツの面々はわざわざゲームを『作らなければ』ならなかったのでしょうか?
近年の日米野球でも、メジャーの面々はわりあい最近まで、日本に観光気分でやってきたこともあったし、追い詰められてから初めて本気モードになり、日本のプロ野球の面々をコテンパンに叩きのめしているところがあります。2002年も日本のプロ野球を”卒業して”メジャーリーガーになったイチロー選手が、メジャーチームの一員として参加し、最初3連敗したのちに4連勝したことについて、『メジャーとしての面子があるから絶対に負け越しはできなかった』と語っているとおり、メジャーリーグ・ベースボールはあくまで日本のプロ野球にとっては『指南役』としての存在であって、決して対等な存在とはいえません。
もちろん、日本のプロ野球にも優れた選手がたくさんおり、彼らに敬意を払う延長で日本のプロ野球に敬意を払ってくれる人もいますが、どこかで日本のプロ野球を蔑んでいる選手がいるなと感じるのは私だけでしょうか?(その理由と是非についてはさておき)
スポーツは勝負、しかも、先輩としての意地があるのなら、もっと勝負にこだわるところがあってもよさそうなものです。しかし彼らは、そういうことをしなかった。それは、彼らが自前のドサ回り球団だったからではないかと『黒き やさしき ジャイアンツ』の著者の佐山和夫さんはその60ページにて語っています。
『この「ロイヤル・ジャイアンツ」が、どこからの招待にもよらない、単なるドサ回り球団であったことも、日本球界にとっては幸運なことであった。その理由の詳しいことについては、この後、引き続いて起る大リーガーたちの「招待野球」との比較において明らかにしたいと思う。
今はただ、自前の旅行団であるがゆえに、彼らには<野球の使節団>という自負もなければ、<指導者>との高飛車な態度もなかったことを指摘し、これが当時の日本人プレヤーに<気楽さ>を与えていたことを記すにとどめたい。』
つまり彼らは、自分たちでわざわざ興行のためにやってきたわけで、お客様を球場に呼ぶために、相手を叩きのめすようなことをやることは到底できなかった、ということです。そしていい試合を演出すれば、相手のいいプレイも引き出せ、試合も盛り上がり、さらに客を呼べるということがわかっていたのでしょう。やはり島津さんの仰るとおり、彼らは『プロフェッショナル』だったのです。
しかしそれだけでなく、彼らをそのようにさせた理由には、次のような理由もあったのではないかと佐山さんは語ります。
『もとより日本には黒人に対する人種差別はなかった。あるのは、むしろ遠来の客人への歓待の情である。本場野球への尊敬の念が、これに輪をかける働きをしていたろう。
日本側がそうである限り、それは旅にある彼らの心に沈み入ったに違いない。それでなくても、彼らはこの地において、思い切り自由の空気のうまさを味わっていたのではなかったか。』
そう、当時のアフリカン・アメリカンは、まだまだアメリカ社会の中で差別されており、アメリカに住みながらにして、『ブラック・アメリカ』ともいえる別世界に住み、別の文化を形成していたのです。それはジャズであり、ニグロリーグであったわけで、その中ではステイタスがあっても、アフリカン・アメリカンお断りのレストランやバスは、それこそアメリカ中にあった。そして彼らニグロリーガーたちは、実力に見合ったステイタスを得られず、不自由な思いをしていたわけです。だからこそ、それに見合った待遇と敬意に出会ったとき、それに対する感謝の念を示した。それが「ゲームをつくった」彼らの態度に表れたのではないでしょうか。
ではいよいよ次回からは、Shinorarさんのリクエストにお応えし、黒人やインディアンも含む野球巡業団に参加した日本人初のプロフェッショナル・ベースボールプレーヤー、ジャップ・ミカドこと三上吾郎さんのお話です。
(2004.10.16.配信)
【参考図書・web】
・黒きやさしきジャイアンツ 佐山和夫著 ベースボールマガジン社