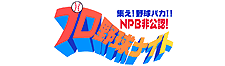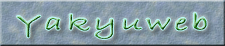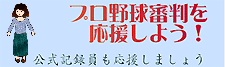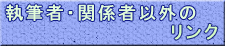俺が好きなスポーツ by ダイスポ 日本スポーツ物語編
●日本スポーツ物語 日本ラグビー物語 〜その1〜
■連載第2回 「日本ラグビー物語:第1話」
■連載第4回 「日本ラグビー物語:第2話」
■連載第6回 「日本ラグビー物語:第3話」
■連載第8回 「日本ラグビー物語:第4話」
第2回 「世界へのチャレンジ:日本ラグビー物語」第1話
(1) ジャパン、ラグビー母国に挑戦
スポーツを愛する皆様、ご機嫌いかがでしょうか。
俺が好きなスポーツ、今回からは「日本スポーツ物語」の第一弾として、ラグビー日本代表の歴史をご紹介してまいります。身体の小さなラガーマン達が、いかにして世界のラグビー大国に立ち向かってきたのか?その苦闘の足跡を振り返っていくことにしましょう。
まずは、今から30年前、1971年の秋へと皆様をお連れいたします・・・
秩父宮ラグビー場は、かつて見たことがないような大観衆で溢れかえっていた。夜7時のキックオフでありながら、午後5時にはスタンドが完全に満員になってしまったのである。それでも押し寄せる人の波はいっこうに退くことを知らず、ラグビー協会は非常措置を取った。なんとスタンド前のフィールドにまで、客席に座れない観客を入れて試合を観戦させることにしたのだ。選手達がなだれ込んでくる危険性があった。それでもファン達は、どうしてもこの試合を見たくてたまらなかったのだ。
ラグビーの母国、イングランドの初来日。日本ラグビー界にとって、待ちに待った大チャンスであった。世界の強豪を相手に自分達がどこまで通用するのか。それを証明する機会が遂に訪れたのだ。
ラガーマン達のイングランドへの憧れは、柔道や空手などの武道を修行する外国人が日本に対し憧れを持つのと似たものがある。今まで対戦したくても叶わなかった、歴史と格式を持つ英国チームとの初対戦であったから、出場メンバーに選ばれた選手達の感激もまたひとしおであった。
1971年9月24日、記念すべき第一戦。花園ラグビー場で行われたこの試合では、日本が終盤まで互角以上の試合を展開した。結局最後に突き放され、19−27で敗れたのだが「日本だってやれる…もしかしたら、次は勝てるかも!」という期待を抱かせるに十分な内容であった。
そして迎えた、29日の第2戦。選手も関係者もその鼻息は荒かった。
秩父宮のフィールドに飛び出す両国の選手達。沸き返るスタンド。舞台は整った。
午後7時過ぎ、試合開始。しかし世界8強の一角であるイングランドにとっても、決して負ける訳にはいかない試合であった。母国の誇りをかけた猛攻撃が日本を襲う。パワーを利した執拗なアタック。日本代表も身体を張ったタックルで大男達をなぎ倒す。どちらも決定的なチャンスが作れない。激しい攻防に、スタンドのボルテージは上がる一方であった。
均衡が遂に破れた。イングランドがペナルティ・ゴールを決め、3−0とリードを奪ったのだ。更に追加点を許し、6−0とされる。日本も反撃を試みるがあと一歩及ばない。そのまま前半終了。
後半に入っても、点が入らない展開が続く。やはり勝てないのか…しかし残り10分、日本に大チャンスが訪れた。後半32分、センター宮田浩二が敵陣を切り裂く。ゴールまであと数メートルのところまで迫った。やった!トライか?だがイングランド選手の決死のディフェンスにより、宮田はゴール寸前で転倒。遂にトライを奪う事が出来なかった。
なおも反撃は続く。34分、日本はペナルティ・ゴールを狙う。蹴るのは山口良治。息を整えて、集中。
キックの体勢に入る。
山口が蹴った。
楕円球は、ゴールポストを通過していった。決まった!
3−6、待望の初得点だ。
試合終盤、なおも激しい攻防は続く。ロスタイムに入り、日本最後の攻撃。しかしこの攻撃も実ることは無かった。
そのまま試合終了。日本3−6イングランド。
日本は勝てなかった。しかし2試合を通じて、イングランドをギリギリまで追い詰める事が出来た。アジアの国が、世界の強豪とも立派に戦えることが証明出来たのだ。
またこの試合を観戦した英国の新聞記者は、本国に向けこう打電したという。「身体の小さな人間のラグビーを、日本は完成させた」。
そして観客たちも、その熱い80分間に酔いしれた。試合終了後、グラウンドになだれ込んだ彼らもまた、歴史の目撃者であった。日本ラグビーが世界を震わせた一夜の目撃者である。
この日本代表チームを作り上げた監督こそ、名将・大西鉄之祐であった。大西はいかにして、日本のラグビーを強くしていったのか?そして彼のラグビー哲学とは、いったいどのようなものだったのか?
お時間がまいりました。続きは、次回の講釈で。
第4回 「世界へのチャレンジ:日本ラグビー物語」第2話
(2)知将・大西鉄之祐のラグビー哲学>
スポーツを愛する皆様、ご機嫌いかがでしょうか。
俺が好きなスポーツ、今回はラグビー日本代表物語の第二回です。日本代表チームを作り上げた名将・大西鉄之祐。彼はいかにして、日本のラグビーを強くしていったのか、そして彼のラグビー哲学とは、いったいどのようなものだったのでしょうか?皆さんと一緒に振り返っていくことにいたしましょう。
1916年、奈良県に生まれた大西は、早稲田大学に入学してラグビーをはじめた。戦後早大ラグビー部の監督に就任した大西は、チームを三度全国制覇に導き、若き指導者として頭角をあらわすことになる。
その頃、大西は彼の人生を変えるような一冊の本と出会った。日本に遠征してきた、英国の名門ケンブリッジ大学の選手が持ってきたラグビー技術書である。南アフリカのラグビー指導者、ダニー・クレイブンが書いたその”Danie Craven on Rugby”を借りて読んだ大西は、最先端のラグビー理論に大きな衝撃を受けた。現在のように、世界のラグビー技術が、アジアの小国・日本にまで入って来なかった時代である。
「このままでは、日本のラグビーは世界にいつまで経っても追いつき追い越すことが出来ない・・・」
焦った大西はラグビー協会関係者に対し、日本代表チームの定期的な編成を提案する。世界のラグビー大国は、揃ってナショナルチームを編成し、一貫した方針のもと強化を進め、定期的な交流を行うことでそれぞれが競い合っている。ところが日本はどうだ。海外のチームが来日したときだけ寄せ集めのメンバーで日本代表を組むだけ、これでは強化などおぼつかないではないか。
もちろん今の様に、海外渡航がかんたんにできる時代ではなかったから、大西の提案がすんなり受け入れられることはなかった。
だが大西の熱意に、ようやく協会も重い腰を上げる。日本代表の強化が、いよいよ本格的に行われることになったのだ。大西は1964年に代表の強化ヘッドコーチ、続いて66年には、遂に日本代表の監督に就任した。
監督に就任した大西が次に行ったのは、日本チームが世界で戦うための戦略作りである。身体の大きな外国の選手に対抗する為には、緻密な作戦を立て、実行していかねばならない。
身体の大きな者に挑む。じつはこれは大西の得意とすることであった。大西の率いていた早稲田チームは、ライバル明治大学より常に軽量の選手が揃っていた。重量を生かしてタテに攻めて来る明治の強力フォワードを、早稲田はヨコの展開「ゆさぶり」で対抗し、成果を上げてきていたのだ。
大西は日本代表の戦いの核となる基本戦術を「展開、接近、連続」と短く言い表した。大西はこう述べている。
「外国人との体力差、特にフォワードにおける差が大きいため、ボールを取れば速やかにバックスに展開し、フォワード戦はさける」
「接近とは、日本人の巧みさを生かしたプレーだ。日本人は短い距離でのダッシュが上手い。彼ら(外国人)が長い槍だとしたら、我々は短刀だ。短刀でヤリと戦うなら、相手のフトコロ深くに飛び込む以外に勝ち目は無い」
「連続とは、全員のフォローによる連続プレーのことだ。身体が小さくても、持久力をつけることは可能である。外国人より早く走り、長く走り、穴を見つけることができるならば、ゲームの主導権は崩れる」
そして大西は、この「展開・接近・連続」理論の実現が出来る選手を広く集め、日本代表チームを編成し、鍛え上げていった。かつてのような寄せ集めチームではもうなかった。
そのころ、日本代表のウィング(チームで最も足が速く、トライを奪う役目のエース的存在)だった坂田好弘は、大西を「関西弁で、大きな身振り手振りでコーチするおもろいオッサンやなぁ」と思っていた。しかし大西は、自分の後輩である早稲田の選手をひいきするわけでも無く、個性を殺して型にあてはめるような指導もしない。当時としては、非常にやりやすいタイプの指導者であった。
大西は練習中に、よく居眠りをした。それで坂田がしめしめ、と思って手を抜くと突然目を覚まし「こら、しっかりやれ!」と叱られる。それが何度も続くので、「大西先生、ホンマに寝てるんかいな…」と疑るようになった。しかしこの坂田が、後に世界に名を轟かす「フライング・ウィング・サカタ」に成長していくのである。
こうして大西に鍛えられた日本代表が、遂にラグビー王国、ニュージーランドに遠征することになった。世界一の強豪を相手に、日本のラグビーは通用するのか?そこで大西が見せた「魔術」とは?エース坂田の活躍は?
お時間がまいりました。続きは、次回の講釈で。
【参考文献は、当シリーズ終了時にご紹介します】
第6回 「世界へのチャレンジ:日本ラグビー物語」第3話
(3)いざ、ラグビー王国へ
スポーツを愛する皆様、ご機嫌いかがでしょうか。
俺が好きなスポーツ、今回はラグビー日本代表物語の第3回です。大西鉄之祐監督率いる日本代表が、遂にラグビー王国、ニュージーランドに遠征することになりました。世界一の強豪国を相手に、果たして日本のラグビーは通用するのでしょうか?
皆さんと一緒に振り返っていくことにいたしましょう。
大西が、世界の強豪と渡り合うために作り上げた「展開・接近・連続」理論。ラグビー日本代表チームは、この理論を理解し実現できる選手のみが選ばれるようになった。それは同時に、それぞれのポジションで当時ナンバーワンのプレイヤーが必ずしも選ばれるわけではないと言うことも意味していた。
しかしあまりにも突飛な選手起用は、時として関係者をも驚かせた。特に1968(昭和43)年の春に行われるニュージーランド遠征のフルバックに、トヨタ自動車の萬谷(まんたに)勝治選手が選ばれたときの衝撃は大きかった。萬谷は、そもそもフルバックが本職では無い。彼は早稲田大学時代からウィングとして活躍していた。フルバックはバックラインの最後方に位置し、守備の最後のトリデとして身体を張ったディフェンスが求められる。また相手がキックで上げてくるボールを、空中で競い合ってキャッチしないといけない。萬谷はスピードこそ豊かだが、168cm、65kgと当時としても小兵の部類に属する選手だった。世界の、とりわけ巨漢揃いのニュージーランド相手に、果たしてフルバックが務まるのか…多くの人々が、大西の決断に疑問の目を向けた。
遠征を前に、ニュージーランドの強豪クラブが来日した。大西はこれを絶好のテストと考えて、自ら全日本学生代表を率いて対戦。「展開・接近・連続」戦法がピタリとはまって、学生代表は30−17で快勝した。相手を完全に翻弄したこの試合を勝って、大西は自信を深めた。いける!これなら、アウェーの試合でも充分戦えるぞ。
日本代表は勇躍、南半球の島国・ニュージーランドへと旅立っていった。
ところが。
やはり、ラグビー王国は強かった。
日本代表は、まず初戦のオタゴ戦を26−33と落とした。次のノースオタゴ戦は5−17、さらに第3戦、第4戦も敗れ、まさかの4連敗を喫してしまうのだ。いかに強豪相手とはいえ、これは予想外の出来事だった。
チームの雰囲気は、当然のように重く暗いものとなっていった。ウィングの坂田好弘は、大西に突然「デメ(坂田のニックネーム)、どうしたら勝てるんや」と話しかけられて驚いた。まさか大西先生が、自分のような若者にこんな弱音を吐くなんて…自信をもって日本代表を作り上げてきた監督が迷っている。チームは、浮上のきっかけを見出せないままでいた。
転機は、意外な形でやってきた。
なんとニュージーランド全土を襲う、大地震が発生したのだ。日本代表の宿泊していたホテルも一部が崩壊し、危うく大惨事となるところであった。しかしこれ以降、まるで悪い憑き物が落ちたかのように、チームは息を吹き返した。第5〜第7戦まで3連勝を記録したのである。もちろん大西も相手の戦法を研究し、ディフェンスを修正するなどの対策を打っていた。決してラッキーなだけの連勝ではなかったのだ。しかしチームが失っていた自信と明るさを取り戻したのが何より大きかった。
とはいえ、手放しで喜んでいる訳にもいかなかった。次の相手は今回の遠征で最も強豪とされる、オールブラックス・ジュニアだったからである。世界最強を誇るニュージーランド代表・オールブラックス。その次代を担う選手達がズラリ揃うチームを相手に、果たして日本は勝てるのだろうか?地元のファンは、まさかジュニアが負けるなどとは考えもしなかった。いや、善戦すら出来ないだろうと予想していた。ある選手などは「ジャパンに勝ち目は無い」とはっきり宣言されたと言う。それくらい、王国の人々は誇り高かったのである。
1968年6月3日、ウェリントン。
日本代表とオールブラックス・ジュニアの対戦する日がやってきた。
秋晴れのウェリントン、会場のアスレチックパークには多くの観衆が詰め掛けていた。
パトカーに先導され、競技場に向う日本代表。舞台は整った。
午後2時半、キックオフの笛が鳴った・・・。
いかがでしたか?いよいよ、日本ラグビー史上最高のゲームをお届けいたします。
しかしお時間がまいりました。続きは、次回の講釈で。
【参考文献は、当シリーズ終了時にご紹介します】
第8回「世界へのチャレンジ:日本ラグビー物語」第4話
(4)ジャパンラグビー最上の日
スポーツを愛する皆様、ご機嫌いかがでしょうか。
俺が好きなスポーツ、今回はラグビー日本代表物語の第4回です。大西鉄之祐監督率いる、ラグビー日本代表試練のニュージーランド遠征。遂に最大の強敵、オールブラックス・ジュニアとの対戦を迎えました。下馬評は圧倒的に日本不利。しかし結果は・・・
それでは、皆さんと一緒に振り返っていくことにいたしましょう。
運命の日、1968年6月3日。
試合会場のウェリントン、アスレチックパークには多くの観衆が詰め掛けていた。もちろん、オールブラックス・ジュニアの勝利を信じるニュージーランド人がその大多数を占めていた。
午後2時半、いよいよキックオフ。
いきなり反則を取られる日本代表、気負いが見える。ゴールを決められ、欲しかった先制点を奪われてしまう(日本0−3NZ)。さらに日本のディフェンス陣の裏を衝いて、NZがバックス攻撃から先制トライ(日本0−8NZ)。さすがはラグビー王国のNo.2チーム、あっという間に8点をもぎ取られてしまった。
日本もやられっぱなしではない。開始直後の混乱からすばやく立ち直り、前半7分に攻撃の司令塔・スタンドオフ桂口力がペナルティゴールを決めて反撃を開始する(日本3−8NZ)。そして相手バックスの強引なアタックに対し、センター横井章が強烈なタックル!その衝撃に思わずボールがこぼれる。
「チャンスだ!」
転々とするボールを拾ったのが、日本のエース、左ウィング坂田好弘だった。そのままゴール右すみに飛び込む。日本、待望の初トライはやはり坂田が奪った。(日本6−8NZ)。
さらに試合は激しく動く。坂田の2個目のトライ、そして横井が25分にもう一つのトライを奪った。司令塔・桂口が敵陣に鋭く切り込み、それに続くバックス陣がスピーディーなパス回しで相手ゴールに迫る。たとえボールを奪われても、今度はハードタックルで相手を倒し、ボールを奪い返してしまう。日本のお家芸である、すばやい攻守の切り替えと連続攻撃が通用したのだ。NZもゴールキックを決めて追いすがる。しかし日本は前半終了間際、横井から坂田につないでゴールラインに飛び込む。坂田、この日3つめのトライ。前半を終え、なんと日本リードのまま折り返すことになったのだ(日本17−11)。
観客席に動揺が走る。これは一体、どういうことだ?ジュニアがジャパンごときにリードを許するとは…ファンが騒ぎ出す、そして関係者の顔がこわばりだした。なんとしても後半は追いつき、逆転せねばならない。王国の名にかけて、東洋からきた挑戦者に汚名を着せられることだけは避けねばならなかった。
ジュニアの猛反撃が始まった。もうなりふり構ってなどいられない。日本の速い出足を止める為に、バックラインの後方に高いキックを上げ、落下地点めがけて突撃する作戦に切り替えてきた。体格差を生かした、日本の弱点を衝く攻撃法だ。そのNZの攻撃を止める防波堤が、フルバック萬谷(まんたに)勝治だった。フルバックとして実績の無い彼がどうしてこの大事な遠征に抜擢されたのか、ラグビー関係者は皆首をひねった。しかしその理由は、この試合を通じて明らかになる。萬谷はNZの怒涛のラッシュをものともせず冷静にボールをキャッチし、相手の攻撃の芽を積んでいったのだ。たとえ上背が無くても、ハラをくくってチームのために身を投げ出せる選手が欲しい。それこそが、大西の萬谷起用の真意であった。キックのたびに突っ込んでくる巨漢達に跳ね飛ばされながら、ボールを決してこぼさないその勇敢さに、NZの選手も観客も舌を巻くしかなかった。
しかし遂に、その萬谷がキャッチミスを犯す。ただ一度の失敗を見逃さないのは、さすがNZの一流選手であった。こぼれ球を拾ってトライ(日本17−16NZ)。とうとう1点差にまで詰め寄られてしまった。追加点を奪わなければ危ない・・・
だがここでも、萬谷起用が大当たりする。彼の持ち味はディフェンスだけではなかった。その豊かなスピードを生かした攻撃参加が見事に決まる。最後は右のウィング伊藤俊幸が独走してトライ(日本20−16NZ)。さらに坂田、なんとこの日4つめのトライまで奪う。日本が23−16とジュニアを突き放すことに成功したのだ。なんと言う攻撃力だろう。NZ、最後の反撃に出る。観衆が悲鳴のような大声援を送る。危ない、ジュニアが敗れてしまう、こんなことは絶対に許されない。それは選手たちにとっても同じことだった。残り5分、必死の思いで1トライを返す。23−19。守る日本、攻めるNZ。パス、キック、ダッシュ、キャッチ、ラン、タックル…もうロスタイムに入っている。あと少しだ。「終わってくれ」「早く試合終了のホイッスルが鳴ってくれ!」防戦一方の日本がボールを奪った、パスから伊藤がキック…笛が鳴った。試合終了だ。スタジアムが静寂に包まれた。日本が、オールブラックス・ジュニアを破った。いや、破ってしまったという表現の方が適切だろう。世界のラグビー史上に残る大番狂わせ、そして日本のラグビー史上、最高の快勝劇であった。
坂田はこの試合を振り返ってこう言う。「あの試合は、試合に出た15人の呼吸があっていて、少しも乱れなかった。あんな経験、後にも先にも一度だけだ。」大西が手塩にかけて育てた日本代表が、遂に世界に衝撃を与えた記念すべき一日であった。
いかがでしたか?この後は、大西監督の弟子たちのその後を追ってみましょう。しかしお時間がまいりました。続きは、次回の講釈で。
【参考文献は、当シリーズ終了時にご紹介します】
●日本ラグビー物語の続きはこちらから。