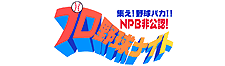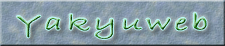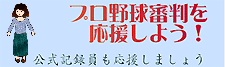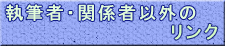俺が好きなスポーツ by ダイスポ 日本スポーツ物語編
●日本スポーツ物語 日本F1物語 〜その1〜
■連載第20回 「日本F1物語:第1話 <日の丸見参>」
■連載第22回 「日本F1物語:第2話 <出会い>」
■連載第24回 「日本F1物語:第3話 <苦闘>」
■連載第27回 「日本F1物語:第4話 <完成>」
■連載第29回 「日本F1物語:第5話 <前進>」
連載第20回 「日本F1物語」第1話 <日の丸見参>
スポーツを愛する皆様、ご機嫌いかがでしょうか。
今回からは新たに「日本F1物語」と題して、ホンダF1チームの挑戦をお送りしたいと思います。日本初のグランプリ・チームとして世界の桧舞台に挑んだ男たちは、いったいどのような人々だったのでしょうか?皆さんと共に振り返っていくことにいたしましょう。
1964年夏、ドイツ・ニュールブルクリンク・・・
決勝スタートの時間がやってきた。
各マシンが、続々とスターティング・グリッドにつく。そのいちばん後ろには、見なれないカラーの車体があった。白いボディに、大きな赤い丸。
そう、日の丸デザインの車だ。お世辞にも、決してカッコ良いとはいえない。
しかしそのマシンを見るや、スタンドを埋めた地元西ドイツの観客から歓声がわき起こった。かつて第二次大戦の仲間だった日本が、敗戦後約20年の時を経て、ついにこのひのき舞台にやって来た。無謀とも言える出走を成し遂げた東洋の挑戦者に対する、あたたかい励ましの拍手であったのか。
あるいは戦勝国・イギリスやさっさと降伏したイタリアのチームに対する、あてこすりの気持ちから来る歓声だったのかもしれなかった。
その光景を見て、ある日本人の記者は感動にうちふるえた。
「ああ、いよいよ日本の車が、この世界選手権の舞台に立ったんだ・・・」記者はそれだけで、もう胸が一杯になっていた。
F1世界選手権シリーズ第6戦、ドイツグランプリ。日本のホンダF1チームが、初めてグランプリに参戦した記念すべきレースであった。
日の丸をかかげて、ホンダのF1カー、RA271が姿を見せたのである。
しかしホンダの監督・中村良夫には、そんな感動にひたっている余裕などなかった。なにしろドイツに来てからというものの、一度として満足な練習が出来ていなかったからだ。けっきょくいちばん後ろからのスタートとなってしまった。 「とにかく、無事に走ってくれ・・・」 中村はじめチームのメンバーは、みな祈るような気持ちだった。
レースがスタートした。ホンダをドライブするのは、アメリカ人のロニー・バックナム。彼もまた、このレースがF1デビューとなる、まったく無名の若手レーサーであった。はじめて実戦を走るマシンに、初めてのF1レース。そんな彼に、多くを求めるほうがどうかしていた。
しかしバックナムは順調に走行を続けた。最後方からどんどん追い上げを見せ、順位を上げていく。 「おお、意外にやるじゃないか…」 客席から驚きの声があがった。そして12周目になると、ついに一ケタ台の9位にまで浮上した。もともとホンダ・エンジンのパワー自体は群を抜いている。トラブルが発生して壊れさえしなければ、じゅうぶん上位を狙える車なのだ。
それに新人・バックナムのこの頑張りはどうだ!残り3周、ホンダチームのピットが色めきたった。 「よし、この調子ならいけるぞ!」
しかし・・・F1はそう甘くはなかった。その12周目、大きくコースを外れてしまったのだ。マシンは大破し、無念のリタイア。中村はクラッシュ地点までかけつけた。バックナムのことが心配だった。マシンはまた作り直せる。しかしレーサーは、決して作りなおすことが出来ない。
幸い、バックナムは無事だった。中村は胸をなでおろした。
そして大破したマシンの横で、バックナムと中村は土手に腰掛けてがっくりと肩を落とした。あと少し、もうほんのひとふんばりで完走する事ができたのに・・・
でも中村は、内心では満足していた。完走こそ逃したものの、自分たちのマシンがF1にじゅうぶん通用することが証明できたからだ。デビュー戦、しかも殆ど何もできなかった予選のことをおもえば、それだけで充分であった。なにより、ここまでの苦難の道を思えば・・・
宿舎に引き上げて来た中村は、主人にチップを払おうとした。
しかし宿のおかみさんは、それを受け取らずに返しに来て、こう言った。「あなた達は頑張ったのに、賞金はゼロだった。ならばこのチップは、受け取ることは出来ない。これは私たちからみなさんへの、ささやかな賞金としておいてください」。
こうして中村良夫を中心とする、ホンダF1チーム戦いの日々が始まったのである。
しかし、ここに至るまでの道のりは、まさに山あり谷ありの遠く苦しくものであった。
なぜホンダはF1を目指したのか?どうやってF1に参戦することが出来たのか?そしていかに、世界の賞賛を勝ち取ることが出来たのか?後に無敵のホンダ・エンジンを作り上げた、その原点とはいったいなんなのか?
お時間がまいりました。続きは、次回の講釈で。
連載第22回:「日本F1物語」第2話 <出会い>
スポーツを愛する皆様、ご機嫌いかがでしょうか。先月から新たにスタートいたしました「日本F1物語」、今回はその第2回です。
日本初のグランプリ・チームとして世界の桧舞台に挑んだ、F1ホンダチームの面々。今回からは少し時計を戻して、彼らが実際にF1に挑戦するまでの苦闘の日々をご覧いただきたいと思います。ホンダのチャレンジは、スムーズに実現したのでしょうか、それとも・・・?皆さんと共に振り返っていくことにいたしましょう。
創業者・本田宗一郎率いる本田技研(ホンダ)は、戦後2輪メーカーとして日本国内で頭角をあらわしていった。そしてホンダは次のステップとして、自社製オートバイによる海外レース界への殴り込みを決意した。激しい闘争心の持ち主である本田宗一郎が、ホンダ製バイクの優秀性を世界に誇示して海外輸出への道を開くべく、2輪グランプリへの進出をもくろんだのは当然のことであったかもしれない。
1954(昭和29)年、日本を襲う厳しい不況の中、ホンダも生産調整を行うなど苦しい経営が続いていた。そんな中本田宗一郎は、イギリスのマン島で行われる伝統のTT(ツーリング・トロフィー)レースへの出場を宣言する。その宣言文は、
「私の年来の着想を持ってすれば必ず勝てる」
「吾が本田技研は此の難事業を是非共完遂し、日本の機械工業の真価を問い、此れを全世界に誇示するまでにしなければならない」
という非常に激しいものであった。そして1959(昭和34)年、ホンダは苦闘の末にマン島レースへの出場を成し遂げ、さらに2年後の1961(昭和36)年には、早くも悲願の優勝を遂げるのである。それも125ccクラスと250ccクラスの両部門で優勝するという文句のつけようが無い内容で、ホンダの勇名はいちやく世界にとどろいた。本田宗一郎の無謀とも思えた挑戦が、現実のものとなった瞬間であった。
後にホンダF1チームの監督を務めることになる中村良夫がホンダに就職したのは、その頃のことであった。第二次世界大戦中は戦闘機の開発に携わった中村だが、戦後は日本内燃機(くろがね)でオート3輪の開発に携わっていた。だがそれは、中村の技術者としての自尊心を満足させてくれるものではなかった。彼が最もやりたかったのは、レーシングカーの開発であった。航空機の開発までは無理としても、レースでなら、自分の腕をう存分振るえると考えたのである。
当時は貴重品だった海外の自動車雑誌に載っているF1やルマン耐久レースの記事は、中村にとっては大きな憧れであり、いつかはこの舞台に俺も立ちたい、自分の作ったマシンでヨーロッパのグランプリ・シーンに乗り込んで行きたいという夢を抱くようになっていたのである。
やがてくろがねの解散に伴い、彼はホンダへの移籍を考えるようになった。だが彼がやりたかったのは、あくまでもレースにほかならなかった。それもホンダが手がけていた2輪ではなく、4輪レースである。もし4輪レースをやれないのなら、俺がホンダに入る意味が無い。中村はそんな思いを胸に、ホンダへと乗り込んでいった。
入社面接の席上。中村は、社長である本田宗一郎と相対した。もちろんこの時が初対面ではあったが、中村は単刀直入に本田に尋ねた。
「本田技研は、本気で4輪レースに進出する気がありますか。2輪グランプリだけではなく、4輪グランプリへの意欲を持っていらっしゃるのでしょうか」
中村の、このちょっと無礼とも思える質問を聞いた本田宗一郎は、中村をまっすぐ見据えて、そしてすかさず答えた。
「出来るかどうか知らんが、俺はやりたいよ」
この一言が決め手となって、中村は本田技研への入社を決意した。そしてF1グランプリ出場への長く、激しくそして苦しい戦いの日々が始まったのである。
こうしてホンダF1チームの重鎮、本田宗一郎と中村良夫は運命的な出会いを遂げました。さぁ中村は、いったいどのようにしてホンダF1出場への道を切り開いていったのでしょうか。念願のF1用エンジンの開発は、スムーズに成功したのでしょうか?
しかし、お時間がまいりました。続きは、次回の講釈で。
(参考文献・資料は本連載終了時にまとめて掲載します)
連載第24回:「日本F1物語」第3話 <苦闘>
スポーツを愛する皆様、ご機嫌いかがでしょうか。
「日本F1物語」、今月はその第3回です。
本田技研は、まず2輪レースの世界において圧倒的な強さを発揮し、世界にその名をとどろかせていきました。そんな中、F1グランプリでの活躍を夢見る男・中村良夫がホンダに入社します。ホンダのF1参戦は、果たしてどのような形で実現していったのでしょうか?皆さんと共に振り返っていくことにいたしましょう。
ホンダが具体的にF1マシンの開発に着手したのは、1963(昭和38)年に入ってからのことである。しかし当時のホンダは、4輪メーカーとしての実績はまだあまり無かった。市販用として軽トラックのAK−360と、小型スポーツカーのAS−500の開発に携わった中村らは、忙しいスケジュールの中F1エンジンの開発にも着手していったのである。市販用自動車でさえ手をつけ始めたばかりなのに、よくもF1用のエンジンを開発しようなどと考えたものだと思う。しかしこれこそが、ホンダという企業の真骨頂であったと言える。F1グランプリという夢の舞台に立つためホンダ入りした中村と、世界への飽くなき挑戦を志向する総帥・本田宗一郎の意志と激しい闘争心なくして、このチャレンジはありえなかっただろう。
一方で中村は、ホンダエンジンを搭載してくれるF1チームを見つけるべく、欧州へと足を伸ばしていた。この事からも分かるように、当初はエンジンとシャシー(車体)の両方を自前で開発する「オール・ホンダF1チーム」の創設ではなく、エンジンのみを開発し、既成のグランプリ・チームに供給してF1に出場するという参戦方式を考えていたのである。
そしてこの東洋からの訪問者に対し、興味を示したのは主に英国のチームであった。イタリアのフェラーリやドイツのポルシェと言ったチームは自社エンジンを搭載するマシンを開発していたので、ホンダには入り込む余地は無かった。だがいくつかの英国系のチームは、2輪レースで欧州を席巻していたホンダがF1に挑戦してくることに対して強い関心を示した。中でもコーリン・チャップマン率いるチーム・ロータスは、ホンダエンジンに対し特に強い興味を持ち、チャップマン自身が来日して「ホンダエンジンを、わがロータスのマシンに搭載したい。ドライバーはジム・クラーを起用する」という熱烈なラブコールを送ったのである。これにはさすがの中村も面食らった。ロータスという名門、しかもトップ・レーサーのクラークを起用する!これは、まだグランプリ・デビューさえ果たしていないホンダにはとっては、あまりにも条件の良すぎる話であった。逆に言え、荷が重過ぎたのである。しかしグランプリ界の大物・チャップマンの情熱と勢いに押し切られた形で、この提携は一気に合意まで至った。新生ロータス・ホンダのデビューは、翌1964年のモナコ・グランプリを目標とすることになった。
いざ決まってしまえば、開発に割くことのできる時間は殆ど無かった。だが中村たちF1開発部隊による必死の努力の結果、ロータスに搭載するエンジン「RA−271E」が遂に完成したのだ。
そうこうしている内に年が明け、ホンダがデビューする1964年がやってきた。中村らは国内テストを行い、本番用のRA−271Eを英国に空輸するところまで漕ぎ着けていた。
ところが。
コーリン・チャップマンから、信じられないような至急電報が届いた。
「・・・チーム事情により、ホンダのエンジンをロータスに搭載することが出来なくなった。なにとぞ悪しからず。」
その電報を読んだ中村は卒倒しそうになり、次いで激しい怒りが湧き起こってくるのを感じた。何てことを言うのだ。レースまであと3ヶ月に迫っているじゃないか。ここまで開発をやらせておいて、今更そちらの都合で『なかった事にしましょう』なんて、そんなバカな話があるか!
しかしカッカしていても始まらない。中村は冷静に、ホンダが次に取るべき行動を考えた。
ひとつは他のチームにエンジン供給を持ちかけること。もうひとつは、今年はグランプリ参戦を諦め、翌1965年から参加するべく再びチームを探すこと。そして最後のひとつは、車体も自前で開発し、オール・ホンダとしてF1に出場することであった。他チームへの提携は、開幕を目前に控えた今となっては無理な話だった。一番無難なのは、参戦見送りだ。しかし中村は、ここまで辛い思いをして、今更諦めるのは絶対に嫌だった。
中村は腹を決めていた。しかし最終決定権は本田宗一郎が持っている。彼は本田にロータスの電報について報告し、そして今後について尋ねた。
本田は一瞬怒りの表情をあらわし、こう言った。「ロータスとやれないからと言って、F1が出来なくなるわけじゃなかろう。俺はやめんぞ!」
これで話は決まった。中村はチャップマンに、たった一行返信した。
「電報見た。ホンダは、ホンダ自身の道を歩む」。
いかがでしたか。こうしてロータスとの提携を絶たれたホンダF1チームは、遂に自前の車体まで開発することになってしまいました。開幕までもう殆ど時間がありません。果たしてホンダのデビューは、一体どうなるでしょうか?
しかし、お時間がまいりました。続きは、次回の講釈で。
(参考文献・資料は、本連載終了時にまとめて掲載します)
連載第27回「日本F1物語」:第4話 <完成>
スポーツを愛する皆様、ご機嫌いかがでしょうか。
「日本F1物語」、今月はその第4回です。
ロータスとの提携で、F1デビューを目前に控えていた本田技研でしたが、突然の破談により、自力でのシャシー(車体)開発を余儀なくされることになってしまいます。残された時間は殆どありません。果たして、ホンダのマシン開発は間に合うのでしょうか?それとも…皆さんと共に振り返っていくことにいたしましょう。
「ホンダは、ホンダ自身の道を歩む」。
ホンダF1チームの責任者・中村良夫がロータスのコーリン・チャップマンにあてた、たった一行の電報。その言葉どおり、ホンダはもはや誰の力も借りる事無く、自動車レースの最高峰、F1へと打って出なければいけなかった。実績も、ノウハウも無い。今なら考えてもむちゃな話だが、それは当時でもほとんど同じ事であった。
中村が監督として、考えなければならないのは以下の事であった。
1.シャシーの設計・開発
2.ドライバーの選定
3.実際のグランプリにおけるチーム運営
4.グランプリ転戦の具体的方法
5.タイヤ、ブレーキの調達
これらひとつひとつが大変な難題である。しかもそれぞれの要素が複雑に絡み合い、その上で勝ち負けを争うのがプロのレーシングチームである。以上の点について何の経験も無いホンダが、グランプリ開幕の数ヶ月前にこれだけの事を考え、そして実行しなければならないのは無謀の一言に尽きた。たとえて言うなら、受験1週間前になって勉強を始め、しかも最難関の東大医学部に合格しないといけないような、まったく途方も無い話であった。
ましてF1部隊は、当時ホンダが進めていた市販車の開発部隊の一環であり、F1の開発だけ行っていればよいわけではなかった。仕事の兼務は当然のことであった。
F1部隊に携わっていた、若手エンジニアの佐野彰一は「チャップマンは逃げたんだ」と考えていた。チーム事情だ、なんだと理由は立ててはいたけれど、要するにホンダのF1エンジンを目の当たりにして、手に負えなくなって放り出したに違いない。
佐野がそう思うのも無理は無かった。当時、ホンダが開発したF1エンジンの形状は「横置き12気筒」。当時としては、これは規格外れの形状、そして馬鹿でかさであり、これを実際に搭載してレースを戦うというのは、とうてい不可能に思われたのである。
しかしロータスが去り、実際に車体を自社で設計・開発せざるを得ない状況の中で、佐野に白羽の矢が立った。佐野は驚いた。ある日突然、F1のボディ設計を命じられたのである。大学を卒業し、ホンダに入社してまだ4年目の佐野にとっては、これはまさに大抜擢であった。佐野は、もちろんF1の車体の図面など書いたことが無かった。そこで図面描きについては専門家が助手につき、設計を手助けした。そこから始まり、ジュラルミンを素材に使用したボディ作りなどを経て、ようやく12気筒横型エンジンを搭載できるボディが完成したのである。全てが手探りの中、開発は進んでいった。それは今のF1マシンの開発から見れば、極めて未熟なレベルであったかもしれない。しかしその分、彼ら開発者たちには、自由な発想で物事を捉え、そしてF1マシンという現実のモノ作りに結び付けていくエネルギーが満ち溢れていたのである。
佐野たちの努力により、遂に本物のマシンが完成した。巨大な横置きエンジンを搭載する為、そのボディも必然的に横幅が大きなものになっていった。F1マシンお披露目の日、その車体を後から見た佐野は、「真四角で、あまりカッコ良いものではないな」と感じた。
ところが、そんな感想では到底済む筈の無い男が一人いた。言うまでも無く、総帥・本田宗一郎である。F1カーが完成したことで最初は機嫌がよかったのだが、その不恰好な車体を見た瞬間、本田の瞬間湯沸し器に火がついた。
「なんだ、この犬小屋みたいなのは!」
この晴れのお披露目に、マシンの車体を撮影する為カメラマンが待機していた。しかし本田の性格を知らないカメラマンは、本田のあまりの剣幕におそれをなし、思わず逃げていってしまったのである。
だが本田とて生粋の技術者である。ただやみくもに怒るだけではなく、自分できちんと対策を考え、それを指示した。短気で口は悪いが、現場の人間と一緒になって、少しでもより良いものを生み出そうとする本田の姿勢がよく覗えるエピソードである。
こうして佐野は、遂に難物のエンジンを搭載するシャシーの開発に成功したのだ。この点だけは、佐野はF1界の大物、チャップマンの上をいくことになった。ロータスが「逃げた」かどうかは定かではないが、彼は最後まで諦めず、遂にその難題を解決することに成功したのである。
いかがでしたか。こうしてホンダF1チームは、遂に自前の車体まで開発することになってしまいました。さぁこのマシンを走らせるドライバーには、一体だれが選ばれたのでしょうか?
しかし、お時間がまいりました。続きは、次回の講釈で。
(参考文献・資料は、本連載終了時にまとめて掲載します)
連載第29回「日本F1物語」:第5話 <前進>
スポーツを愛する皆様、ご機嫌いかがでしょうか。
「日本F1物語」、今月はその第5回です。
ロータスと袂を分かち自前のF1マシンを完成させた、中村良夫率いるホンダF1チーム。このマシンを走らせるドライバーは、一体誰に決まったのでしょうか。そして運命のデビュー戦を迎えるまでに、どのようなことがホンダチームに起こったのでしょうか。皆さんと共に振り返っていくことにいたしましょう。
中村は、1964年1月にロータスとの提携話が無くなったとほぼ同時期に、独自のドライバー探しをはじめていた。とはいえ当時の中村には「グランプリ・ドライバー」と言っても、非常に漠然としたイメージしかなかった。中村は3つの可能性を考えた。
1. 現役F1レーサーの獲得
2. ホンダ2輪チームのグランプリ・レーサーを転向させる
3. 他のカテゴリーからの抜擢
現役のグランプリ・ドライバーの中で最有力なのは、米国のフィル・ヒルであった。元世界選手権王者であるヒルが、ホンダF1プロジェクトに関心を持っていたからだ。しかしグランプリにこれからデビューするホンダにとって、フィルはいささか大物過ぎる存在であった。F1未体験のホンダにとって、経験豊富なフィルに振り回されるのは避けたかったのである。
次に2輪チームからの転向。ホンダにはマイク・ヘルウッドという、F1への関心が非常に高いエースライダーがいた。彼は2輪の世界ではチャンピオンであり、中村としても彼の起用を一度は考えた。これが一番容易な方法であることに違いはなかった。しかし2輪と4輪では、同じモータースポーツでもまるで性格が違う。もちろん、ヘルウッドたち2輪レーサーの才能は買うが、中村が求めていた人材はあくまでも「早期に勝てる」望みのある4輪ドライバーであった。2輪レーサーの起用は見送られた。
とすれば、残るは可能性ある新人ドライバーの抜擢しかない。日本には、残念ながらF1マシンを乗りこなし、世界の強豪レーサーに伍していけるだけの技量を持つ者がいなかった。一方、欧州にはF2、F3などの下部カテゴリーがあり、F1チームとの契約を目指して激しい戦いを演じている。しかし中村には、彼らとのコネクションが無かった。あとは消去法でアメリカである。中村はアメリカ・ホンダにレーサーの紹介を依頼した。そして送られてきたリストの中から、中村が選んだのはロニー・バックナムという男であった。アメリカ・ホンダ側としても、バックナムが最も良いだろうという判断であった。中村はバックナムとの契約を結んだ。
レーサーは決まったが、まだやることはたくさん残されている。まずは整備基地の確保。これは当時稼動し始めていた、ホンダのベルギー工場の一角を貸してもらうことで解決した。次にグランプリの転戦の問題。こちらはフランスのホンダを通じ、ワロン・トランスポートという会社が見つかり、F1カーとエンジン、スペアパーツなどを積み込む移動用の大型バンを用意してもらえることになった。さらに懸案のタイヤとブレーキも、英国のダンロップ社から供給してもらう話がまとまった。
グランプリ・デビューまで時間が無い上に、こうしたチーム運営に全くノウハウの無いホンダにとっては、全てが手探りの上での歩みであった。その割には、ここまでの歩みは異常とでも言うべき速さであった。もちろん、マシンの開発を進めながらの話である。
3月に入ると、F1レーサーのジャック・ブラバムが来日し、テストカーであるRA-270を試乗した。続いてバックナムも来日、RA-270を試運転した。彼にとってF1カーのドライブは初めてであり、まずは慣れてもらうことが第一であった。必ずしも有意義なテストが出来たわけでは無いが、それでも様々な問題点を抽出して解決することが出来たという点においては有意義である、と中村は考えていた。それに実際のグランプリを走るドライバーが来日しテストしてくれるというのは、F1チームのスタッフにとってはプロジェクトの進行に手ごたえを感じるという意味でも、大変な進歩であった。
実戦に投入するのは、RA-270ではなく、最新型RA-271であるが、この時点では未完成であった。中村はホンダのF1デビューを、当初7月のイギリス・グランプリと予定していた。しかし開発面の遅れから見ても、この計画は実現不可能であった。そこで予定を変更し、8月のドイツ・グランプリでのデビューに照準を絞った。そして271型の完成を待たず、バックナムを引き連れ5月にはヨーロッパに渡っていた。実際のグランプリ出場に向けて、現地でやらねばならないことがあったからである。それと同時に、7月下旬にRA-271をオランダでテストし、それから翌月のドイツ・グランプリデビューというスケジュールが決まった。
さぁいよいよ、ホンダがF1の本場、ヨーロッパに殴りこみを賭けるときがやって来ました。彼らは、一体どのように迎えられたのでしょうか。そしてRA-271は、ドイツ・グランプリデビューに間に合ったのでしょうか?
しかし、お時間がまいりました。続きは、次回の講釈で。
※第6話〜第10話はこちらから。