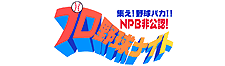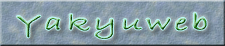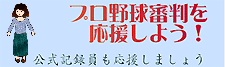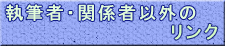俺が好きなスポーツ by ダイスポ 日本スポーツ物語編
●日本スポーツ物語 日本F1物語 〜その3〜
■連載第40回 「日本F1物語:第11話 <Veni Vidi Vici>」
■連載第42回 「日本F1物語:第12話 <3リッター元年>」
■連載第44回 「日本F1物語:第13話 <改革>」
■連載第46回 「日本F1物語:第14話 <モンツァの激闘>」
■連載第47回 「日本F1物語:第15話 <悪夢>」
■連載特別編 「日本F1物語:最終回 <ラストラン>」
連載第40回「日本F1物語」:第11回 <Veni Vidi Vici>
スポーツを愛する皆様、ご機嫌いかがでしょうか。「日本F1物語」、今月はその第11回です。F1参戦2年目を迎えたホンダF1チームは、それまでチームを引っ張ってきた中村良夫がチームから退き、不振が続いていました。果たしてホンダは、このまま低迷を続け一度も勝たぬまま、シーズンを終えてしまうことになるのでしょうか、それとも・・・皆さんと一緒に振り返ることにいたしましょう。
本田宗一郎は、ベルギーGPの入賞にも満足していなかった。すぐさま自分の片腕である河島喜好を、次の開催地であるイギリスに派遣し、ホンダチームにカツを入れさせた。
本田の怒りがただ事でない事を知ったチームは、このレースに非常体制で臨むことになった。これまでのロニー・バックナムとリッチ−・ギンサーの2台エントリーから、ギンサーのみの1台出走に切り替えたのだ。バックナムのマシンに割く力を全てギンサーに投入することで必勝を期したのだ。バックナムはここでも扱いが悪かった。ギンサーでマシンを熟成し、勝負はバックナムで賭けるつもりだったが、ここでもその構想は破られる事になったのである。
だがその甲斐あってか、予選でギンサーは3番手の好タイムをはじき出した。この結果はチーム全体に自信を取り戻させた。今後こそ行けるぞ!…しかし、結果は26周目でリタイア。続くオランダGPもギンサーの1台エントリーで出場したが、結果は辛うじて6位で勝ち点1、トップからは周回遅れと言うありさまであった。このままでは、今季中の優勝などとてもおぼつかない…危機感をさらに募らせたホンダは、続くドイツGPを欠場し、イタリアGPに向けてエンジンの大改造を行う事にした。
ギンサーは、レース中エンジンの温度が上がっていくにつれ、加速のパワーが下がっている事を指摘していた。この問題をどうやって解決していけばよいのか?中村の考えでは、レースを休むのではなく、むしろ参戦しながら問題を解決していくべきだと思っていた。テストでは、本当にレースの実情に合わせた問題点を抽出し、解決する事は出来ないと考えていたからだ。しかしチームの決定は、一度レースを休んでその間に改修作業を行うと言うものであった。中村は不満であったが、今やチームの監督ではないので何の決定権も持ち合わせておらず、怒っても仕方の無い事であった。
同じ頃中村は、本社の首脳陣から監督への復帰を要請された。本来なら願っても無い話ではある。だが中村は、その話を聞いてカッとなった。そちらの都合で監督の座から降ろしたくせに、上手くいかないからって再び監督に、とは一体どういうつもりなのだろうか。それはあまりに、虫が良すぎる話ではないか。
「お断りしますよ。今のチームは、私が考えていたものとはまったく違ったものになっています。今更私の出る幕なんてありませんね」。中村はそういい残して席を立った。
マシンの大改造は、とりあえずイタリアGPに間に合った。そして再び、ギンサーとバックナムの2台エントリーに戻された。しかし結果は、2台ともエンジン・トラブルによるリタイア。この結果を見て、チームのメカニックも、そして日本のスタッフも心の底から落胆した。イタリアGPまでの2ヶ月間、殆ど不眠不休で作業を行ってきたにもかかわらず、エンジンの問題は全くと言ってよいほど解消されていなかったのだ。これ以上、一体どこをどう直せば良いと言うのだ?これまで誰の手も借りず、自分たちだけで道無き道を歩いてきた。しかし今、果てしない暗闇の中に立たされて、もうどうしたら良いのか、チームの誰もが本当に分からくなってしまっていた。
1965年のシーズンは、残り2戦。ヨーロッパラウンドは既に終了し、アメリカGPとメキシコGPを残すのみとなっていた。アメリカGPには、遂に総帥・本田宗一郎自身がサーキットに姿を現した。しかしそれも特効薬にはならず、ギンサーが7位でなんとか完走したものの、優勝したグラハム・ヒルには2周遅れと言うありさまであった。
最終戦メキシコGPの前、中村は自ら首脳陣に監督復帰を申し出た。いったんは断った話ではあったが、もう我慢出来なかった。中村は監督就任と同時にすぐさまメキシコに飛ぶと、チームのメンバーを集めて話をした。
「次のレースは必勝体制で臨む。チームの編成もガラッと変える。ホンダ社内の序列は関係無い、勝つために適材適所の人員配置を行う。たとえ会社では上役でも、チームではチーフ・メカニックに抜擢した下の者に従ってもらうから」と宣言したのだ。メンバーに新たな緊張感が加わった。そして中村は高度にあり気圧の薄いメキシコに合わせて、エンジンの混合比の変更を行った。また燃料噴射セッティング等、その他の設定変更も行い好感触を経た。
レースが始まった。信じられない光景がそこには広がっていた。ギンサーがあっと言う間にトップを奪い、その差をどんどん広げていくではないか。レース終盤に入ると2位以下の猛追を受けたものの、ギンサーは序盤のリードを守りきってチェッカー・フラッグを受けた。勝った、遂に勝ったぞ!中村に、コースからピットへ戻ってきたギンサーが抱きついた。そしてそれに続くかのように、メキシコの熱狂的な観衆が彼らを祝福しようと押し寄せてきた。その群集をかきわけるかのように、一人の男が中村に近づいてきた。誰あろう、ロータスの総帥、コーリン・チャップマンであった。
「ナカムラ、おめでとう!」チャップマンの祝福を受けて、中村はロータスと決別した日のことを思い出していた。ホンダは、ホンダの道を歩む・・・そして今日、遂にホンダは世界の頂点に立ったのだ。バックナムも5位に入賞した。中村はサーキットから、すぐに日本のホンダ本社に電報を打った。それはたった一行、”Veni, Vidi, Vici”(来た、見た、勝った)という、ジュリアス・シーザーの言葉を引用したものであった。
本社でマシンの開発にあたっていた佐野彰一はレース当日、まさかホンダが優勝するなどとは夢にも思わず、自宅で休んでいた。そこに会社から連絡が入った。「今からメキシコ料理店で祝勝会を行うから、すぐにこいよ」。だが佐野としては、会社を休んでいたのに今更祝勝会だけ行くというのも気まずく、この誘いを断る事にした。しかし佐野としても、今までの苦労が報われた嬉しい瞬間であることに、違いは無かった。1965年10月24日、遂にその日はやって来たのである。
いかがでしたか。ホンダは遂に、シーズン最終戦にして優勝を成し遂げましたね。では3年目は、一体どんなシーズンになっていったのでしょうか。念願の年間総合チャンピオンへの道のりは・・・
しかし、お時間がまいりました。続きは、次回の講釈で。
(参考文献・資料は、本連載終了時にまとめて掲載します)
連載第42回 「日本F1物語」:第12回 <3リッター元年>
スポーツを愛する皆様、ご機嫌いかがでしょうか。「日本F1物語」、今月はその第12回です。1965年の最終戦、メキシコGPで劇的な初優勝を果たしたホンダF1チームは、いよいよ参戦3年目の1966年シーズンを迎えました。そしてこの年のF1は、ある大きな節目を迎えていたのです。その節目とは一体なんだったのでしょうか。皆さんと一緒に振り返ることにいたしましょう。
1965年10月、メキシコGPの終了時点では、ホンダF1チームは翌66年に使用するためのマシン開発に殆ど着手していなかった。社内の事情から、グランプリを転戦しながら次の年に走らせるマシンを同時進行的に開発する事は困難だったのである。また翌年からは、1.5リッターエンジンから3リッターへと、排気量が一気に倍増する事が決まっていた。中村良夫は、ホンダ以外のどのチームも3リッターへの移行は苦労するはずで、シーズン開幕当初からきっちりと3リッターエンジンを搭載したマシンを実戦投入させることの出来るチームは無いと見ていた。従って本格的なマシンが出てくるまでは、どのチームも間に合わせの改造エンジンを搭載した車で出てくるものと踏んでいたのである。
ならば、ホンダとしても焦る必要は無い。66年シーズンの参戦は、他チームの新型マシンが出揃うまで見合わせ、その間にじっくり開発に取り組めば良いと中村は考えていた。
という訳で夏までに新型3リッターマシンの開発を終え、秋のイタリアGPに参戦するという大まかな開発プランを立てた。またホンダ社内でも、3リッターF1の開発優先順位は低かった。まずはホンダにとって重要な収入源となる、量産機種の軽自動車開発、続いてF1と同時進行で開発されていたF2が第2位。F1マシンの開発は、なんと6位に追いやられていたのである。しかしこれは、仕方の無いことであった。2輪メーカーから4輪自動車メーカーへの脱皮を狙っていた当時のホンダにとって、売れる車を開発する事は最重要課題であったのだ。
この辺は本田技研の副社長で本田宗一郎社長の懐刀である、藤沢武夫副社長からの要請であることは間違い無かった。F2に関しては、前年からジャック・ブラバムと取り組んでいたプロジェクトであり、マシンも熟成して勝利の可能性が高かった為、優先順位も高かった。そして3リッターF1エンジンの開発は、まだ入社3年目の入交昭一郎が担当する事になった。F1チームに加入したばかりで経験の浅い入交にとって、これは大変しんどい仕事であった。
中村の予想通り、他のF1チームの新型マシン開発も遅れていた。移行に失敗し苦しむチームが多かったが、そんな中比較的スムーズに3リッターへの移行に成功したのは、ホンダと共にF2にも参戦していたブラバムであった。ブラバムは7月のフランス、イギリス、オランダGPを立て続けに勝つと、8月のドイツGPも制して破竹の4連勝を記録、年間優勝が現実のものになってきた。ブラバム・チームはホンダと組んだF2ではさらに強く、向かうところ敵無しの快進撃ぶりであった。
そしていよいよ、3リッターエンジンを搭載した新型マシンRA-273が完成し、当初の予定通りイタリアGPに出走する事が決まったのである。8月の中旬には鈴鹿サーキットでリッチー・ギンサーによるテストが始まったのだが、肝心の中村はまたも監督の座から外れていた。中村が現場での指揮を取れないことに対しギンサーは不安だったが、それは中村も同じ事だった。案の定その不安は的中し、)月のイタリアGPでギンサーはクラッシュ、負傷してしまったのであった。続く10月のアメリカGPにはギンサーとロニー・バックナムの2台体制で臨んだが2台ともリタイア。ホンダのエンジンはパワーだけなら他のチームを圧していたが、肝心の安定性に欠けており、更なる熟成が必要であった。次は最終戦のメキシコGP、昨年ギンサーが初勝利を挙げた思い出の国である。ここではギンサーが4位に入り、RA-273にとって初の入賞を果たした。しかし、昨年のような勝利の味にはやはり程遠いものであった。66年シーズンは、未勝利のまま終わる事になったのである。ワールドタイトルは、ブラバムが手にした。
さて監督の座を離れている中村ではあるが、ホンダの苦戦に対しただ手をこまねいて見ていた訳ではなかった。既に夏ごろから、ある重要な人物と来季の構想について話をすすめていたのである。その人物とは、サーキットの大物、イギリスのジョン・サーティースであった。サーティースは2輪グランプリで世界チャンピオンになった後4輪に転向。1964年にはフェラーリに乗りF1の世界でもワールドタイトルを獲得する事に成功した。この年のタイトル争いは大変な激戦となり、最終レースであるメキシコGPの最終ラップまで行方のわからないスリリングな展開の末、サーティースが辛くもタイトルを獲得したのであった。ともあれ、2輪と4輪、両方で世界チャンピオンになった唯一の男として、サーティースは生きながら既に伝説の男であったと言えよう。
そのサーティースから、翌67年はホンダのマシンでレースを戦いたいという話が持ち込まれたのであった。66年のサーティースは、前年までと同様フェラーリのドライバーとして開幕を迎え第2戦のベルギーGPを制した。たが、その後チームと対立してフェラーリと決別。クーパーのマシンで以降のレースに出走し最終戦のメキシコGPに優勝、年間順位でもブラバムに次ぐ2位に食い込んでいた。
中村とサーティースの間で話はまとまり、1967年シーズンからサーティースのホンダ加入が決まった。「ただし」サーティースは中村にこう付け加えた。「私のホンダ加入のために、一つだけ条件があるんだ。それはナカムラ、あなたが再びチームの指揮を取ることだよ」。
という訳で、水面下では67年シーズンを巡る駆け引きが始まっていました。果たしてホンダの67年シーズンは、一体どうなったのでしょうか?
しかし、お時間がまいりました。続きは、次回の講釈で。
(文中敬称略。参考文献・資料は本連載終了時にまとめて掲載します)
連載第44回 「日本F1物語」:第13回 <改革>
スポーツを愛する皆様、ご機嫌いかがでしょうか。「日本F1物語」、今月はその第13回です。モータースポーツ界の大物、ジョン・サーティースを陣営に引き入れることに成功したホンダF1チーム。参戦4年目の1967年シーズンでは、一体どのような出来事が彼らを待ち受けていたのでしょうか?皆さんと一緒に振り返ることにいたしましょう。
サーティースを獲得したホンダだが、中村良夫にはあと一つ、気の進まない嫌な仕事が待ち受けていた。それは、現在のドライバーであるロニー・バックナムと、そしてリッチ−・ギンサーの二人に対する解雇通告である。中村自身の言葉を借りて言えば、彼は「首切り役人」にならないといけなかったのだ。1966年メキシコ・グランプリはクーパー・マセラティに乗ったジョン・サーティースが制した。ギンサーは4位、そしてパックナムは8位に終わっている。
レース終了後、中村とギンサー、そしてパックナムの3人はロサンゼルスに飛んだ。そして中村は、来季のホンダF1チームの体制を2人に伝えた。今まで苦楽を共にして来た仲間に引導を渡さないといけない、なんとも辛い瞬間であった。中村は、なぜサーティースと組む事に意義があるのか説明した。F1チームが、これ以上日本の本社に負担をかけるのは避けたい。そのためには欧州、具体的にはイギリスに前線基地を持ち、チーム運営の大半をまかなえるような体制を取りたい。その為には、自らレーシング・チームを所有しており、しかもレース界の実力者であるサーティースと組む事が最も好都合だったのである。
中村の説明を聞くと、二人ともすぐに納得した。クビになると言えば確かに重い話だが、こういうことはレースの世界では日常茶飯事なのである。ウェットな感情が入り込む余地など無かった。バックナムはホンダがF1にデビューして以来、嫌な思いも何度か経験しながらここまで一緒に進んできた。ギンサーはメキシコGP優勝という、ホンダの、いや日本のモータースポーツ史上に残る不滅の金字塔を打ち立てた男である。だが彼らの役割は、この66年シーズンをもって終わったのだ。二人は本当のプロフェッショナルであり、その事をすぐに理解した。3人はホンダの健闘を祈って乾杯し、これからも友情の続く事を誓い合った。
こうしてドライバーは、正式にサーティースへと交代した。ホンダの1967年シーズンに臨む体制は、以下の通りとなった。
1. ホンダ本社はエンジン、ギアボックスなどの基幹部門のみ開発を担当する
2.それ以外の、車体も含めた開発は可能な限り英国のホンダチームで行う。サーティースは、ロンドン郊外にあるチーム・サーティースのスペース半分と、そして必要なメカニックをホンダに提供する。
3. サーティースが提携しているレースカー開発のロ−ラ社が、ホンダに対し必要な技術的アドバイスを有料で行う。
4. 優秀なメカニックであるジム・ポットンの獲得。
5. チーム運営費は、オイルやタイヤ会社との契約金でまかなう。スポンサーの獲得にはサーティースも協力する。
これで中村が夢にまで見た、レース専門のプロ集団がようやく完成したのである。そしてサーティースは全てを承諾したが、その条件として「ナカムラがチームの指揮を取る事」との約束を取り付けたのだ。中村以外に、このプロの戦闘集団を率いる事は出来ないと考えていたのである。
1967年シーズンが始まった。初戦の南アグランプリはトラブル続きで冷や汗をかいたものの、サーティースの健闘により3位入賞。まずまずの成績であったが、ここからホンダは低迷を続ける。モナコGPはリタイア、そして6月のオランダGPでも完走することが出来なかった。そしてこのオランダでは、フォード・コスワースDFVエンジンがデビューを飾った。DFVは本格的な小型軽量で新型エンジンの割には割合に安定性もよく、このエンジンを搭載したジム・クラークの乗る新型マシン、ロータス49があっさり優勝を飾ってしまう。次のベルギーでも、ホンダはリタイア、フランスではベルギーで壊してしまったエンジンの代替機が間に合わず出走を見送った。サーティースは度重なるトラブルにより、すっかり東京のホンダ本社に対する不信感を持つようになってしまった。中村はこの難局を乗り切るため、プラグの変更、またシーズン中としては異例であるが、タイヤをグッドイヤーからファイアストーンに変更するなど必死の挽回作業を行い、なんとか復帰戦のイギリスGPでは6位入賞に漕ぎ着けた。
だが戦闘力の高い、コスワースエンジンを搭載するロータスとの戦力差は明らかであり、早急に対抗策を練らないといけないのは確かであった。しかもそれは付け焼刃的な小手先の変更ではなく、抜本的なマシン大改造に取り組む必要があったのである。ホンダエンジンも出力は最高に良かったがあいかわらず車体重量も重く、せっかくのパワーを相殺していたのである。またレースが既に進行中であり、残された時間は少なかった。
いかがでしたか。大物サーティース加入にもかかわらず、なかなかホンダの成績は上向いていきません。果たして中村は、一体どんな対策を打ったのでしょうか?
しかし、お時間がまいりました。続きは、次回の講釈で。
(文中敬称略。参考文献・資料は本連載終了時にまとめて掲載します)
連載第46回 「日本F1物語」:第14回 <モンツァの激闘>
スポーツを愛する皆様、ご機嫌いかがでしょうか。「日本F1物語」、今月はその第14回です。大物ジョン・サーティースを陣営に迎え入れたホンダF1チームでしたが、1967年シーズンも苦戦が続いていました。この状況に、彼らが打った手は一体何だったのでしょうか。皆さんと一緒に振り返ることにいたしましょう。
イギリスGPでは入賞を果たしたホンダだったが、戦闘力の高いコスワースDFVエンジンを積むロータスとの差は明らかであった。もはや現在のRA-273では立ち打ちできない。中村良夫はこの現状を打破すべく、新たなマシン開発を決意していた。かといって、日本の本社にはあまり頼りたくない。英国で彼らが出来ることといえば、軽量のシャーシーを製作する事であった。幸い、ホンダが提携しているロ−ラ社にはインディカー用として開発されたマシンT−90があり、この車を改造してF1に実戦投入する事になったのである。ロ−ラ社もこの作業に全面協力してくれる事になった。中村は日本から佐野彰一をイギリスに呼び、開発に携わらせる事にした。
佐野は67年の初夏、イギリスにやって来た。なんとしても新型シャーシーを、9月に行われるイタリアGPに間に合わせたいという命を受けていたのだ。時間が無い中、最善の結果を出していく仕事には慣れていた。だがホンダとローラの技術者では車作りに関する姿勢が違っており、佐野は新鮮な驚きを覚えた。多くの専門家や職人たちが、てきぱきと自分たちの仕事をこなしていくのにも感銘を受けた。
中村がイタリアGPで新型マシンの投入を決意したのは、開催地のモンツァが高速コースであり、ホンダエンジンに向いていると判断したからである。幸いにもロ−ラのスタッフ達が、熱心に開発に取り組んでくれたおかげで、なんとかそのメドがつきそうになってきた。そこで8月のドイツGP迄はRA−273で戦い、その次のカナダGPは出走を見送って開発・総仕上げに全力投入する事にしたのだ。ドイツではサーティースが4位に入賞した。その天才的ドライビングもさる事ながら、新しいマシンが出来るんだと言うスタッフ全員の熱意が波及した事も大きかった。
それから8月も終わろうとする頃、遂にマシンは完成した。70kgもの軽量化に成功、出来上がりは上々であった。それでもロータスなどに比べるとまだ重く、テストする時間も殆ど無かったが、中村は手ごたえを感じていた。そして新型マシンの名前をRA-300と名付けた。273から一気に300へとジャンプしたのは、今までの枠から離れて新たな勝負をかけるんだ、という意気込みの表れであった。
9月、イタリアGPが開幕した。ホンダとローラの合作マシンを見て「ホンドーラ」とか「ホンド−ロ」などと揶揄する口さがない連中もいたが、中村は気にしなかった。ただ予選でトラブルが相次ぎ、満足なデータを得る事が出来なかったのは痛かった。予選首位はロータスのジム・クラーク。予選2位には、ホンダとも親しいジャック・ブラバムが入った。3位はニュージーランド出身のブルース・マクラ−レン。サーティースは9位に入るのがやっとであった。
レースが始まった。序盤から激しい首位争いが繰り広げられる。ブラバムとチームメイトのデニス・ハルム、ロータスのクラークとグラハム・ヒルの4人が先頭集団を形成する。
クラークが遅れを取った。ピットインの際、タイヤ交換に時間を食ってしまったのだ。だがそこから猛烈な挽回を見せて、再び順位を上げていく。遅れて走行していたサーティースは、エンジンをいたわりながらトップ集団の動きを冷静に見ていた。いたずらに勝負をしかけるような事はしなかったが、それでも3位に浮上していた。
レースは中盤以降、過酷なサバイバル戦の模様を呈していた。ハルム、マクラ−レンが相次いでリタイア。先頭はヒル、ブラバムそしてサーティースという順位だったが、一方ではクラークが猛然と追い込みを見せていた。そして59周目、ヒルのエンジンが突然火を噴いてリタイア。ここでクラークがサーティースとブラバムを抜き首位に立った。クラークの神がかり的なドライビングに、スタンドを埋めた大観衆は沸き立った。だがサーティースとブラバムもレースを諦めない。
そのクラークが突然ペースを落とした。ガス欠による失速だ。これでロータスは優勝戦線から脱落した。残ったブラバムとサーティースの二人は、優勝に向けて猛烈な戦いを演じる。観衆は、前年までフェラーリのエースだったサーティースを応援、愛称「ビッグ・ジョン」を連呼していた。逃げるサーティース、追うブラバム。しかしブラバムがどんどん差を詰めていく。遂に最終コーナー、ここには、リタイアしたヒルのマシンが撒いたオイルが残っていた。ブラバムのマシンがバランスを失う。だがすぐに態勢を立て直してゴールラインをめざす。負けじとサーティースがアクセルを踏み続ける。ホームストレート、2台のマシンがゴールラインをほぼ同時に駆け抜けた。勝ったのはサーティースか、それともブラバムか?チェッカーフラッグ!
サーティースは、ブラバムに僅か0.2秒の差を付けてゴールを通過した。薄氷を踏む思いの、しかし最高に劇的な勝利だった。マシンは興奮した観衆に取り囲まれ、サーティースは彼らに表彰台へと運ばれていった。サーティ−スは「ナカサン!ナカサン!」と中村の名を連呼したが、中村は観衆からマシンを守る事で精一杯であった。だがこうして、ホンダのグランプリ通算2勝目は達成されたのである。
いかがでしたか、遂にホンダが2勝目を挙げましたね。だが翌年、彼らをかつてない激震が襲います。それは一体何だったのでしょうか?
しかし、お時間がまいりました。続きは、次回の講釈で。
(文中敬称略。参考文献・資料は本連載終了時にまとめて掲載します)
連載第47回 「日本F1物語」:第15回 <悪夢>
スポーツを愛する皆様、ご機嫌いかがでしょうか。「日本F1物語」、今月はその第15回です。モンツァでのF1史上に残る激しいバトルを制し、通算2勝目を挙げたホンダF1チーム。翌1968年には、一体どのような出来事が彼らを待ち受けていたのでしょうか?皆さんと一緒に振り返ることにいたしましょう。
イタリアGPを制したジョン・サーティースは67年、年間ランキングでも4位に入る20ポイントを挙げてシーズンを終えた。来る68年はホンダとしても、最終目標であるワールドタイトル獲得を狙う年になるはずであった。チームを率いる中村良夫は、念願であったレース専用の前線基地を英国に築き上げており、世界王座奪取へ手ごたえを感じていた。経験を積んだホンダ・レーシングは、もはや欧州の名門チームにもひけを取る事の無いプロ集団へと成長を遂げていたのだ。
一方、ホンダの総帥・本田宗一郎は決して満足していなかった。何から何まで、自前で作らないと気がすまない本田にとっては、ローラとの合作で「ホンド−ラ」と揶揄されたようなマシンで勝っても嬉しくは無かったのである。そしてその頃、本田は新たなエンジンの開発に心血を注いでいた。それは完成すれば今までの常識を打ち破る、画期的なエンジンとなるはずであった。
F1エンジンは通常、ラジエーターを用いた水冷式が用いられていたのだが、本田は空気を直接送り込むことにより冷やそうと考えていた。水冷式にかわる、空冷式F1エンジンの開発だ。このプランに、本社の技術者たちは仰天した。空冷式は確かに2輪で採用されているが、オートバイと4輪車では構造が違う。また当時、市販車での空冷エンジンが開発されていたが、それと大排気量のF1とでは全く事情が異なっていた。F1エンジンは発熱量が非常に高いので、安定した冷却機能を持つ水冷式が殆どであった。過去には空冷F1が登場した事があったが、その時は芳しい成績を収める事が出来なかった。しかも冷却ファン無しの自然冷却方式を本田は構想していたのである。これは全く前例が無かった。しかし本田の強い意志により、空冷マシンの車体及びエンジン設計・開発に多くの力が割かれる事になってしまった。
中村としても、従来式の水冷エンジンを搭載した新型マシン、RA-301を開発しようと目論んでいたのだが、本社で空冷F1を開発している事は知っていた。そして空冷RA−302の開発に研究所のエネルギーが注がれ、301の開発が遅れているのに怒りを覚えた。水に頼らず、空気を直接送り込んで冷却するという理想を追いかけるのは良いが、それを何もF1で導入するなどと言った、わざわざ手間のかかることをする必要など無いではないか。そんなことに時間とエネルギーを費やすよりも、戦闘能力の高い水冷マシンを開発・熟成して勝利を得ることの方が、今は大切なのに・・・強硬に反対したものの、空冷F1の開発は続行された。中村は、ただ歯軋りするだけであった。また研究所でも、空冷F1エンジンの開発には手を焼いていた。
開幕した新シーズンは、既存のRA−300で臨んだがこちらの成績も悪く、チームは悪循環に陥っていた。水冷RA−301はスペインGPから実戦投入されたが、熟成不足は明らかであり、スペインと次のモナコをリタイアという形で終わった。さらにベルギーGPではトップを独走していたにもかかわらずここでもリタイアと、勝てたはずのレースを落としてしまったのである。
次のオランダGPも勝てずにイギリスへ戻って来た中村に、日本から知らせが入ってきた。空冷F1が完成し、間もなくイギリスへ来るというのだ。中村は気が狂いそうになった。RA−301だけでも既に手一杯なのに、この上どうやってRA−302の面倒まで見ろというのだ。サーティースも、ホンダの姿勢には憤りを感じていた。それでも英国のシルバーストーン・サーキットで、空冷マシンのテストを行う事になった。いざ走ってみると、マシンの加速は問題無いのだが、それもエンジンが冷えている間の話であり、オーバーヒートすればそれまでだった。このオーバーヒートを解消しない限り、実戦投入は無理であった。
ところがこの空冷RA−302が、次のフランスGPに突如出走することになったのである。本社の意向を受けたホンダ・フランスと、主催者側の折衝の末、英国ホンダ・レーシングの全く預かり知らぬ所で決められたことであった。中村はフランスGPの会場であるルーアンに来てから、この事実を知らされて愕然とした。そしてRA−302には、フランス人のベテランドライバー、ジョー・シュレッサーが乗ることも決まっていた。中村は怒り狂い、レースに出場せずにイギリスに帰ることを決意したが、それを制止したのはサーティースだった。サーティースの説得を受けてようやく頭を冷やした中村は、空冷のほうをホンダ・フランスに委ねる事にしてRA−302の出走を受け入れた。ただし中村はシュレッサーに対し「まだレースに耐えられる車ではないので、決して速く走らせないように」とのアドバイスを送った。シュレッサーもこの指示を受け入れた。
7月7日、雨の降る中レースは決勝を迎えた。シュレッサーは中村の指示を守り、後方で周回していた。だが2周目、ヘアピンの地点から黒い煙が上がっているのが見えた。中村は咄嗟に、シュレッサーだと直感的に思った。その通り、RA−302がスリップして土手にぶつかり、大破したのである。レース序盤で燃料をたっぷり積んでおり、マシンはあっという間に火に包まれた。消火隊が駆けつけたものの、もはや手遅れであった。シュレッサーは還らぬ人となってしまったのである。
レース後中村は、シュレッサー夫人と一緒に泣いた。今はもうそれしか、他にすることが無かった。中村の胸中には、強引に出走を取り決めた者への激しい怒りが込み上げてきた。だがかけがえの無いレーサーの命を失った後では、全てが後の祭りであった。中村はあの時、ルーアンに立ち上った黒煙を、生涯決して忘れる事が出来無かったという。それはまさに、悪夢としか言い様が無い悲劇であった。
いかがでしたか。次回はいよいよ、この「日本F1物語」のラスト・エピソードとなります。どうぞお楽しみに。
(文中敬称略。参考資料・文献は、連載終了時にまとめてお知らせします)
連載特別編 「日本F1物語」:最終回 <ラストラン>
スポーツを愛する皆様、ご機嫌いかがでしょうか。昨年よりお送りしてまいりました「日本F1物語」、いよいよラスト・エピソードを迎えることになりました。ジョー・シュレッサーが事故死するという衝撃的な事件が発生したホンダF1チームは、その後どのような運命を辿ったのでしょうか。皆さんと最後まで見届ける事にいたしましょう。そのあとは、ホンダ第1期F1プロジェクトに携わった人々の「その後」にも触れてみたいと思います。
シュレッサーが命を落としたフランスGPにおいて、水冷F1マシンRA-301に乗るジョン・サーティースは必死のドライビングを見せ、2位に食い込んだ。それでも不完全な空冷F1が無理やり出場することを許し、その結果ドライバーが事故死すると言う最悪の結末に終わった事は、ホンダチームの人々をしばし放心状態に追い込んでしまった。この沈痛なムードを払拭する為、中村良夫は新たな賭けに出た。マシンにウィングを取り付けてみたのである。技術的に新しいものを導入する事で現状を打破し、悪い流れを一掃しようと目論んだのであるが、イギリスGPではそのウィングにトラブルが発生してしまった。サーティースは奮闘したが、それでも5位に食い込むのがやっとであった。
さらに、中村の気持ちを憂鬱にさせることが起きた。あの忌まわしい悪夢を招いた空冷F1が、再び日本から送り込まれてきたのである。空冷エンジンを強引に推進する本田宗一郎は、シュレッサーの死を知っても決して諦めなかったのである。前年に優勝したイタリアGPの開催地であるモンツァで出走すべく、改良を加えられてきた空冷RA-302ではあったが、実際にコースを走らせてみたところ、熟成の進んだRA-301よりも6秒も遅いタイムしか出せなかった。低速では非常にスムーズな走行を見せるのだが、高速になると相変わらずオーバーヒートしてしまい、車体のコントロールが困難になってしまうのはシュレッサーの車と同じであった。問題点は全く改善されていなかったのである。中村は、このような「厄介物」を何時までも押し付けられることが嫌で仕方が無かった。
だが結局、RA-302は実際のレースを走らなかった。予選ではサーティースが絶好調で、2位のブルース・マクラーレンを抑えてポールポジションを獲得した。だが、肝心の決勝では他の車との接触事故を避ける為ガードレールに激突、あえなくリタイアに終わっている。F1グランプリは、この後欧州を離れて北米ラウンドに入ったが、サーティースはカナダGPでもリタイア。だがアメリカGPでは3位に入り、遂にシリーズ最終戦のメキシコGPを迎えることになった。メキシコでは、ある男が「ホンダの車に乗せて欲しい」と申し出てきた。男の名はジョー・ボニエといった。このボニエこそ、ホンダが初めてドイツGPに参戦した4年前、「経験の無いホンダと、ロニー・バックナムを走らせるのは危険だ」と主催者にいちゃもんをつけたF1ドライバーズ協会の会長を務めていた男であったのだ。
中村とサーティースは検討の末、ボニエにスペアカーを貸し与えた。決勝では、サーティースはリタイアしたが、ボニエは5位に食い込む活躍を見せて2点をゲットした。ボニエは上機嫌で「これは本当に素晴らしい車だね、エアコンさえ付いていればマイカーにしたいくらいだよ」とジョークを飛ばした。
こうしてホンダの1968年シーズンは、全てが誤算の中終了した。シーズン開幕前は総合優勝も出来ると目論んでいたのに、終わってみればサーティースのポイントはわずか12点、ランキング7位という結果しか残すことが出来なかった。勝てたと思うレースを何度も落とし、さらに水冷と空冷、全く形態の異なるエンジンを持つ2つのマシンが同一チームから出走するという異常事態。そしてそれが巻き起こした、ドライバーの死と言う取り返しのつかない悲劇。あらゆる事が裏目に出続けた。だが、それこそがレースという「生き物」の真実であり、あらゆる困難を乗り越えてこそワールド・チャンピオンになれるのだということを、中村は思い知らされたのである。
中村は、ホンダが68年限りでF1から撤退する事を発表した。ホンダが本格的な4輪メーカーになる為には、本社は市販車の開発に力を注がねばならず、これ以上レースを続けるのは無理である、という理由からだった。だがその為に、中村は英国にプロのレース集団を築き上げてきたのだ。しかも負けたまま、F1を撤退するというのは残念で仕方がなかった。中村はせめてもの抵抗として、撤退ではなく「一時休止」と言う言葉を用いている。しかし記者会見に臨みながら、中村はむしろサバサバした気持ちであった。寂しさを感じないのが、自分でも不思議なくらいであった。ロータスとの提携が破談になり「ホンダは、ホンダ自身の道を歩む」とロータスの総帥、コーリン・チャップマンに電報を打った。あれから5年間、中村は、持てる力と情熱の全てをF1チームに注ぎ込んで来たのだ。その意味では、悔いはなかった。
その後中村は、RA-301と共にインディアナポリス・モータースピードウェイに向かった。ホンダF1マシンが、オーバル(楕円)コースでどれだけ走れるか確かめておきたかったのだ。ラストランとなるマシンを操るのは、あのロニー・バックナムであった。バックナムは、ホンダF1チームの誕生と、その最後を共に飾ったという事になる。こうしてホンダは、グランプリシーンからその姿を消した。
ホンダ・レーシングの物語は、これで終わりである。だがこの物語に登場した、主な人物達のその後を簡単に記しておこう。まずホンダに初勝利をもたらしたリッチー・ギンサーは1989年、59歳でこの世を去った。そして2年後の91年には、本田宗一郎も84歳で死去している。中村が本田技研へ入る時、将来F1をやるつもりがあるのかと尋ねると、本田は「出来るか出来んか知らんが俺はやりたいよ」と語った。その二人の夢は立派に実現したのである。レースに対する姿勢の違いから二人は激しく衝突したが、エンジニアとして理想を追い続けた本田と、あくまで勝つ事を目指した中村の二人無くして「日の丸F1」の誕生はなかった。
さらに92年4月には、バックナムも亡くなった。晩年は視力を失うなど、決して恵まれた人生ではなかったようだ。だがズブの「F1素人」を起用した、中村の期待に見事に応えて奮闘したバックナムもまた、日本のF1史上に確かな足跡を残したレーサーだと言えるだろう。
この間、日本のF1を取り巻く環境も大きく変わった。1976年には、日本初のF1グランプリが富士スピードウェイにて開催。80年代に入るとホンダが、今度はエンジン供給という形でF1の舞台に復帰した。そして87年、中嶋悟がロータス・ホンダから日本人初のF1フル参戦を果たす。鈴鹿サーキットでは日本GPが毎年開催され、フジテレビが全戦中継を開始して爆発的なF1ブームが起こった。アイルトン・セナとアラン・プロストを擁するマクラーレン・ホンダは無敵の強さを誇った。ホンダ以外の日本企業も様々な形でグランプリへ参戦し、鈴木亜久里や片山右京など、後に続く日本人レーサーも誕生した。日本のF1界は、大きくその姿を変えていったのである。
それでも、中村達が成し遂げてきた仕事が色褪せることは無かった。情報もノウハウも無かった時代に、世界の桧舞台へ乗り込んで強豪たちと互角に戦って見せた彼らの歩みは、やはり日本のスポーツ史上に残る一大事業であったと言えるだろう。「ホンダ・ミュージック」と称えられたそのエンジンの美しい音色は、60年代のF1グランプリと共に生きてきた人々の記憶に、今もしっかりと残っているに違いない。中村良夫は、1994年にこの世を去った。彼は著書「フォーミュラワン」の冒頭にこう書き記している。
「F1・グランプリは、F1・マシンという人間が作り出す最高のハードウェアと、グランプリ・ドライバーという最高の人間ソフトウェアが合体してはじめて『勝つ』ことができる、人間スポーツの最高の場である」。
<日本F1物語・完>
●本連載の為に使用した参考文献・資料
「F-1 GRAND PRIX:ホンダF1と共に1963〜68」 中村良夫著 三樹書房、1998年
「F1地上の夢」 海老沢泰久著 朝日文庫、1993年
※この2冊が主要文献となりました。これらの本無くして、本連載執筆は不可能でした。第1期ホンダF1の活動に興味を持たれた方にはお奨めいたします。
「フォーミュラワン:18年の集約1977〜94」 中村良夫著 三樹書房、1994年
『1965年第10戦メキシコGP』『1967年第9戦イタリアGP』「激走!F1」 スポーツグラフィック・ナンバー編 文春文庫ビジュアル文庫、1991年
「F1の科学:技術の極限を解剖する」 檜垣和夫著 講談社ブルーバックス、1993年
「経営に終わりはない」 藤沢武夫著 文春文庫、1998年
「ホンダ神話:教祖のなき後で」 佐藤正明著 文春文庫、2000年
「Racing On」 260号(1999.1.23)
●参考web
「Honda F1ルーツ紀行」本田技研工業ホームページ
※本連載でも登場した佐野彰一さんのインタビューや、インディアナポリスを走行した時のエピソードなど、興味深いエピソードが満載です。
JOHN SURTEES GrandPrix.com
JOHN SURTEES International Motorsports Hall of Fame
F1 DataWeb
Express F1
The Formula One DataBase
Grand Prix History
Honda: F1 Legend.com
ATLAS F1